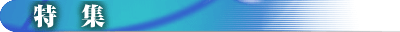
| バックナンバー一覧 >> 2016 Vol.28 No.9 >> 特集 |
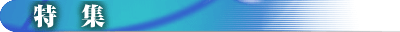 |
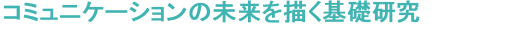 近年のAI(人工知能)技術の発展により、生活や仕事のあり方が大きく変化する中、改めてコミュニケーションの本質が問われている。本特集では、NTTコミュニケーション科学基礎研究所による未来のコミュニケーションの礎となる最新の研究成果を紹介する。 |
通信からコミュニケーションへ――データの時代におけるパラダイムの変容
AI(人工知能)技術の進展と期待の中で、通信からコミュニケーションへのパラダイムシフトが起こりつつあります。こうした中で、NTTが取り組んでいるAI関連の研究開発戦略を紹介するとともに、NTTコミュニケーション科学基礎研究所で現在進みつつある研究を紹介しながらコミュニケーション科学の果たす役割と将来像についても考えます。 |
携帯電話や放送をきれいな音で伝えるための音声音響符号化技術
現在のスマートフォンどうしの通話では多くの場合VoLTE方式が使われており、これまでの固定電話や3G携帯電話(フィーチャーフォン)よりも、より自然な音声で会話を楽しむことができるようになっています。また、IPTVをはじめとする放送においても音声の高品質化が計画されており、より臨場感の高いコンテンツを楽しむことができるようになります。本稿ではこのような高品質な音源を伝送するための基礎技術である音声音響符号化技術について紹介します。 |
膨大な情報の組合せから楽々学習
2次の多項式回帰では、要因の組合せを考慮することで線形回帰(1次の多項式回帰)よりもデータに適合したモデルを得ることが期待できますが、要因数が多くなると組合せ数が膨大になり実現が困難になります。本稿では、NTTコミュニケーション科学基礎研究所が開発した要因数が多いデータでも組合せを効率的に扱うことで解析を可能にし、初期値非依存な学習アルゴリズムにより解析結果を得るのを容易にするConvex Factorization Machines(CFM)を紹介します。 |
気軽に雑談できるシステムの実現をめざして
ここ数年で大きく進歩し、一気に身近な存在となってきた雑談システムですが、音声認識誤りや扱える話題の範囲の狭さなど、まだまだ課題も多く残されています。本稿では、雑談システムの発話内容の改善および実ロボットへの搭載に関する取り組みと、ロボットを複数体としたときの対話破綻回避効果について紹介します。 |
ことばの発達、日本語と英語で何が違う?
1〜2歳ごろの初期の語彙発達において、日本語を習得する子どもは英語を習得する子どもに比べて、語の獲得が緩やかであり、発話できる語彙数が少ないことが知られています。一方で、日本語児は新しい語を正確に学習する能力を早期から持つことが分かってきました。なぜ、日本語児は語の学習が正確なのに発話できる語彙数が少ないのでしょうか。本稿では、その謎を探るために、日本語児と英語児に対する母親の発話スタイルを比較し、子どもの語の獲得との関係を検討した研究成果について紹介します。 |
スポーツ選手の脳情報処理過程を解明するバーチャルリアリティ技術
スポーツで勝つためには、頑健な「体」だけでなく、優れた「技」や動じない「心」を備えることが重要です。これらは脳の情報処理によって支えられていますが、従来の計測手法でその仕組みに迫るには限界があります。NTTコミュニケーション科学基礎研究所では、バーチャルリアリティ技術を用いて、スポーツ選手の生体情報をセンシングし、勝つための脳情報処理のエッセンスを解読することをめざしています。 |
みまもメイト:「見守る側」と「見守られる側」をつなぐICTツール
本稿では、うつ病患者の家族介護者を支援するために開発した介護記録用Webアプリ「みまもメイト」の紹介とそのホームユース調査について報告します。ホームユース後のインタビューから、家族介護者がみまもメイトを利用することによって、自身の介護活動を客観的に見つめ直す効果や、家族介護者とうつ病患者間のコミュニケーション改善に効果があることが分かりました。 |
| □主役登場 |
|