2024年6月号
トップインタビュー
「全社員マーケッタ」で臨む 人と地球にやさしいSocial Well-beingな未来の実現

2023年、新たに発足したNTT研究開発マーケティング本部。従来のプロダクトアウトをベースとした研究開発とマーケティングの融合による新たな価値創造をミッションに掲げ、わくわくするような未来の創造に臨んでいます。大西佐知子NTT研究開発マーケティング本部長にNTTグループの研究開発マーケティングトップとしての心構えを伺いました。
NTT常務執行役員
研究開発マーケティング本部長
大西佐知子
PROFILE
1989年日本電信電話株式会社に入社。2016年NTT 新ビジネス推進室 地域創生担当 統括部長、2020年NTTコミュニケーションズ 取締役ビジネスソリューション本部 第三ビジネスソリューション部長、2021年同 執行役員 ビジネスソリューション本部 第三ビジネスソリューション部長を経て、2023年6月より現職。
NTT初の新組織「研究開発マーケティング本部」発足
研究開発マーケティング本部について教えていただけますでしょうか。
NTT研究開発マーケティング本部は、2023年6月に新たに発足しました。これまで研究所をマネジメントしている研究企画部門、そして、NTTグループの新しい事業を展開していく新ビジネス推進部門は独立して機能していましたが、これを1つに合わせて研究開発マーケティング本部を組織しました。ミッションはこれまでのプロダクトアウトをベースとした研究開発とマーケティングの融合による新たな価値創造です。
さて、1890年、今から133年前に最初の電話が生まれ「つなぐ」テクノロジが始まりました。この電話第一号ができてしばらく後の1948年に逓信省電気通信研究所が発足しました。光ファイバの研究も1966年に始まりました。人と人をつなぐ技術が、人と情報、人とモノ、リアルとバーチャルをつなぎ、伝えるものも音から映像、データ、そして技能や経験、空間をも伝えることができるようになります。そして、光の研究から50年を経てIOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想へとつながりました。研究所発足当時は想像もつかなかったテクノロジの進化です。一方外部環境は、地球環境や社会構造、地政学等のさまざまな変化と、そうした中での人々の価値観は多様化し、物質的な満足度から心の充足度へのシフト等大きく変化してきています。
こうした変化の中で、これまでのようなアプローチだけでは、マーケットの期待を充足することが難しくなってきました。そこで、マーケットのニーズやインサイトをいかに取り込みながら研究開発を発展し、マーケットアウト=市場創造ができるか、といったことに着目して私たち研究開発マーケティング本部が発足したと考えています。
研究開発マーケティング本部はどのような構成なのですか。
本部は研究企画とマーケティング、アライアンスの3部門で構成しています。従来からの研究企画部門に加えて、今回初めてマーケティング部門が誕生しました。例えば、従来のプロダクトアウト型で生み出した新たな技術を実用化していく段階にマーケットインの視点を加えることで、社会実装、マーケットアウトにつながる技術として、より進化できると考えています。具体的には、誰に、どのような価値軸で、何を特徴として市場に訴求していくのか等の視点で研究開発技術をブラッシュアップし、マーケットへアラインしていきます。また、マーケットや技術動向等から洞察し、有望な研究開発領域を導出することもマーケティング部門のミッションだと考えています。そのためにNTTのプロダクトサービス、顧客基盤、人材等のケイパビリティと、マーケットや外部環境をデータによって可視化し、データドリブンで有望な領域を導き出せるようなマーケティング基盤の構築も進めています。
また、変化の激しい市場の中では、NTT単独でのマーケットアウト、イノベーションには限界があります。そこで、さまざまなパートナーと連携、共創していくことで、研究開発の成果を1から10、10から100へと大きくしていくことを担っているのがアライアンス部門です。
アンコンシャス・バイアスを打破して新しい価値を創造する
いわばこれまでNTTグループに点在していた精鋭が結集しているわけですね。この布陣の強みを教えていただけますか。
多様な人々の価値観に対して、わくわくしながら、または安心して利用し続けたいと思っていただけるようなサービスや価値をいかにつくり続けるかという意味では、マーケティング部門にはさまざまな視点が必要です。この意味では現在のメンバには研究者、アライアンスのビジネスを手掛けていたメンバ、プロダクトを開発していたメンバ、そしてNTTグループ外の他社でキャリアを積んできたメンバもいます。また年代やライフステージも多様です。さまざまな立ち位置でビジネスを担ってきた、そしてさまざまな生活感を持ったメンバが、多様な視点を持ち寄っています。これは非常に大きな強みです。
一方で、こうした多様な視点を具体的なマーケティング機能に置き換えて活動や成果に結びつけるフレームワークは組織、構造的にもこれからです。まずは、マーケットインの概念や認識を合わせていくことが重要だと思っています。そして、従来からのプロダクトアウトの視点とマーケットインの視点双方が両輪で機能することで、イノベーション、マーケットアウトを加速できると考えています。
プロダクトアウト視点はどちらかというと「機能軸」、マーケットインの視点は「価値軸」でとらえていくことだと考えています。例えば、この2つの視点を、自転車を例にとってお話しします。まず、「あらゆる道でタイヤがパンクせずに動く」、もしくは「ペダルを軽く踏むとスピードがでる」というのが機能軸の視点ですね。機能軸のみで磨こうとすると、例えばタイヤの耐久性を追求し、タイヤを太く、厚くするということが考えられるかもしれません。一方の価値軸視点では、「駅までの距離が遠いので歩くよりは少しでも移動時間を短くしたいが自動車だと置く場所がない」、または「重い荷物を運べる」、「子どもを保育園に送り届けるためのもの」等、利用する人や状況により求められる価値が変化しますし、その価値を実現するには、自転車以外の手段でも可能だったりします。そう考えると、もしかしたら、タイヤの耐久性を磨いてタイヤを太く、厚くするよりも、もっと別の要素を磨く必要があるのかもしれない、そのほうが、より使いたくなるような、マーケットから求められる技術やプロダクトに昇華していくのかもしれないのです。つまり、視点を変えると、磨いたり、追求したりするポイントが異なってくるのではないかと思っています。メンバの多様な背景、視点を活かして、今磨いているプロダクトを「価値軸」の視点で俯瞰して、今までと違う磨き方が必要なのかを検討したり、別の磨き方により新たな輝きを生み出すことができるのではないかと考えています。
ただ、こうした新しい視点を取り入れていくにあたり、どうしてもこれまでやってきた考え方や手法にとらわれてしまいがちといいますか、経験や知見によるアンコンシャス(潜在的)なバイアスがかかってしまい、新たな視点を組み込んでいくことはなかなか進みにくいこともあると想定しています。それをいかに払拭しながら新しい価値観や視点を研究開発から事業化プロセスへ組み込んでいけるか、時間がかかることだと思いますが真摯に取り組んでいきます。

NTTの新しいプロダクトが次々と発表されていますが、中でもIOWNとtsuzumiは国内外の注目を集めていますね。マーケティング視点でこれらをご紹介いただけますでしょうか。
IOWNは構想が発表されてから5年目を迎えました。IOWNは、ゲームチェンジを興す新たな社会インフラとしてのテクノロジとしてその名称は浸透しつつあり、まさに構想から実現の段階にきています。2023年3月にNTT東日本・西日本よりIOWN APN1.0がサービス開始し、2024年3月にはNTTコミュニケーションズが、お客さまの通信インフラに対する高度化ニーズに対応した都道府県間をまたぐ通信サービス「APN (オールフォトニクス・ネットワーク) 専用線プラン powered by IOWN」の提供を始めています。
つなぐテクノロジの深化、プロダクトアウトの研究成果により生まれたIOWNは、電力効率を100倍にし、伝送容量も125倍にし、技術革新によりデータドリブンなデジタル情報社会を、省エネルギーで実現することでサステナブルに支えます。これがプロダクトアウトの視点でとらえたIOWNです。このIOWNがどのような社会課題を解決することにつながり、どのような価値を人々の生活に生み出していけるのか、これがマーケットインの視点です。あらゆる情報がデジタル化され、IOWNにより低消費電力・高速・高効率でAI(人工知能)が機能できるようになることで、「可視化」「最適化」「パーソナライズ化」を実現し、フードロスや衣料品ロスをなくす等の新たな価値を創造します。そして、その価値は、衣食住から、ヘルスケア、エンタテインメント等の社会生活の中で、Humanity、人間の五感に回帰しながら1人ひとりのWell-beingを実現しながら、地球にやさしいSocial Well-beingな未来を創造することにつながるのではないかと考えています。
そして、ChatGPT等、既存の生成AIと比べて小規模・軽量でありながら世界トップレベルの日本語処理性能を持つ大規模言語モデル(LLM:Large Language Models)「tsuzumi」も、2024年3月にNTTデータ、NTTコミュニケーションズから商用化しました。2023年11月に「tsuzumi」を発表して以来、企業のお客さまや自治体様をはじめ、500件以上におよぶご相談をいただいております。そのうち、3分の2が、お客さまの社内データをLLMに学習させ、カスタイマイズしたLLMを活用したいというものでした。また、幅広い業界からご相談いただき、製造、自治体、金融といった機密性の高いデータを取り扱う業界が多いという特徴が見受けられます。利用用途としては、コールセンタなどのお客さま接点での活用によるCX(Customer eXperience)向上や、議事録自動作成、要約や業務マニュアルからのQ&A作成などの社内業務改善によるEX(Employee eXperience)向上、IT運用自動化やソフトウェア開発などの分野で「tsuzumi」に期待いただいています。今回3月の「tsuzumi」の商用化にあたっては、こうしたお客さまの反響、ご期待、ニーズ等を反映してソリューションメニュー化いたしました。これも、先ほどご説明したマーケットインの視点を組み込んだ研究開発マーケティング本部としての新たな取り組みの1つです。
「tsuzumi」は、海外からも強い関心をいただいています。今後は業界・業種特化型のLLMを多言語で対応し、NTTのアセットに組み込んでグローバルマーケットでもご利用いただけるようにしていきます。「tsuzumi」はあくまでAIという手段の1つです。「tsuzumi」をトリガに、さまざまなDX実現、CX向上をご支援し、人と地球のために、持続可能な世界の実現に向け挑戦を続けていきます。

フラット・コミュニケーションとオープン・マインドで正のスパイラルを生み出す
これまで手掛けてこられたビジネスを踏まえて、トップとして大切にされていることをお聞かせください。
私はこれまで事業会社において、新しいビジネス創造や新サービスの開発に関する業務を中心に手掛けてきました。例えば「電話の次に来る収益の柱となるようなサービスの創出」等といったミッションだったり、インターネットがダイヤルアップから定額制に代わる際にフレッツサービス(フレッツADSL、Bフレッツ等)の立ち上げに従事しました。また、東京オリンピックの開催決定を受けてNTTブロードバンドプラットフォームに新たに設置されたスタジアムWi-Fi推進室では、サッカー場等のスタジアムに、スポーツ観戦が今以上にわくわくし、感動体験となるようなITツールの導入を、先行している米国への視察もしながら、促進することに注力しました。大事にしてきたことは、利用する側のユーザ視点です。どうしても新たなビジネス創造や新サービス開発のプロセスでは、提供者視点のみ、プロダクトアウトに偏りがちになります。どうしたら「売れるか」ではなく、ご利用いただくユーザ視点で、「どうしたら利用したくなるか」の観点を常に心掛けるようにしてきました。その意味では、自らが、利用者であること、つまり自らが利用したくなる、わくわくするかどうかを判断軸に入れるようにしていました。
研究開発マーケティング本部長を拝命し、マーケティングを事業プロセスに機能していくにあたり重要なのがまさにユーザ視点、生活者視点です。そのためには、仕事において私自身も社員もWork in Lifeの姿勢でありたいと考えています。
従来社会は仕事とプライベートは別のモノとすべきという感がありましたが、仕事をしていることがプライベートにも良いシナジーを生みますし、プライベートが仕事に良いシナジーを生むという逆もあります。どうしても忘れがちですがNTTの社員である私たちがテクノロジや人材、社会インフラにつながる価値を提供していく先には、私たちNTTの社員も生活者として存在するのです。その意味で私たちは生活者としての視点を持ち込むことができますし、そのリアルな視点をいかにビジネスに展開していくかが大切なのです。例えば、産休や育休をしっかりと取得するよう世の中が変化してきていますが、実際に取得したときは、会社人ではなく完全に1人の生活者としての視座を得ます。こうしたことをとおして、生活者のリアルな視点に立脚したマーケティング活動につながると考えています。長年、マーケティングのために市場調査をしてきて、実体験と調査結果が乖離していることも身をもって感じていますし、調査には限界があるとも思っています。だからこそ、多様なNTTグループ全社員34万人が生活者としての視点や感性をビジネスに反映させるため、「全社員マーケッタ」となることが重要なのです。
例えば私たちはスマートフォンを日常的に使い、その便利さを享受しているにもかかわらず、ビジネスとしてスマートフォンを売ろうとするとなぜか「どう使う」から「どう売ろう」という視点にすり替わってしまう。これを変えていきたい。
だからこそ、研究開発マーケティング本部のメンバが日々楽しく仕事できるようにと思っています。

トップとして心掛けていらっしゃることはありますか。
フラット・コミュニケーションとオープン・マインドです。情報は、できるだけフラットに共有し、背景や目的等周辺情報も伝わるようにしています。リモート環境が整っていますので、全メンバがTeamsでつながる時間もつくりやすくなりました。タウンミーティングを開催し、メンバへ直接一次情報を共有するようにしています。また例えば、仕事の上下関係とは違う新しいメッシュな関係を築き、話しやすい環境をつくることで職場にだんだんとフラットなコミュニケーションが生まれてきます。その結果、提供側視点のみならず生活者視点でのアイデアも話しやすくなります。
島田明社長の「EXはCXを向上させる」というメッセージも浸透しています。研究開発の皆さんには、研究所発足から社会インフラとなるテクノロジを生み出した素晴らしい実績の蓄積と歴史があり、今回発表した「tsuzumi」もその研究成果があってこそという自負を持っていただきたいと思います。そのうえで新たにマーケットインの視点を加味し、マーケットや社会をみて、新しい価値創造という点でわくわくするような研究や技術開発をしていただきたい。お客さまやパートナーの皆様には、食からヘルスケアまでさまざまな領域で、ぜひ一緒に社会課題解決をめざし、1人ひとりのWell-beingと、地球にやさしいSocial Well-beingな未来を実現していきましょう。
(インタビュー:外川智恵/撮影:大野真也)
インタビューを終えて

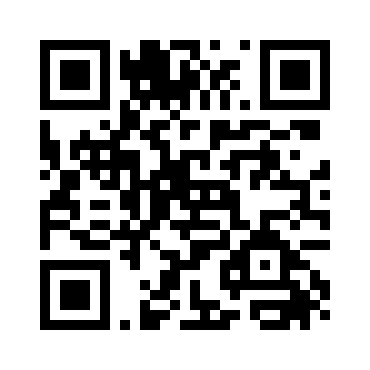




トップインタビューはトップの魅力に加え、課題に感じられていることもしっかり伺います。大西本部長ももちろん課題についても語ってくださいましたが、なぜかそれを課題と全く感じさせず、前向きですでに出口に向かって進んでいるようにも思えます。どんなことでも昇華されるご姿勢は何がきっかけとなったのかを伺いました。お子さんを遅い時間まで預けていることに罪悪感を抱いていた大西本部長が、お子さんを迎えに行ったときのこと。「遅くなってごめんね」と謝るとお子さんが「迎えに来てくれてありがとう」と返してくれたそうです。そのときに「ありがとう」と言われることをしようと心に決め、今日まで積み重ねてこられたと言います。
「考えは言葉となり、言葉は行動となり、行動は習慣となり、習慣は人格となり、人格は運命となる」。マーガレット・サッチャーの言葉、米国の哲学者・心理学者ウィリアム・ジェームズの言葉等諸説ありますが、私はこの言葉を大切にしていますと穏やかに語られる大西本部長。日常の1つひとつの考え方が自分のみならず周囲にも大きな影響を与え、社会を築いていくと実感したひと時でした。