2025年4月号
トップインタビュー
通信設備は経済の「神経系」 つなぎ続けるマインドを胸に地域密着で業務を展開
時代の変化に合わせて「通信」を進化させ、「つなぐ」ことで新たな「あたりまえ」を生み出し、より豊かな社会づくりに貢献しているNTT西日本。これまでの「あたりまえ」である社会の礎としての「通信」を24時間365日守る使命に加え、暮らしやビジネスにおいて新たな「あたりまえ」を創造し、支える桂一詞NTT西日本 代表取締役副社長に設備分野の現状と展望を伺いました。
NTT西日本
代表取締役副社長
桂 一詞

PROFILE
1992年日本電信電話株式会社入社。2012年NTT西日本 設備本部ネットワーク部企画部門長、2020年NTT西日本 取締役 設備本部サービスマネジメント部長、2023年NTT西日本 代表取締役常務 設備本部長を経て、2024年4月より現職。
災害対策に盤石な体制で臨む設備本部のトップとして
副社長に就任され1年が経ちました。振り返られてこの1年はいかがでしたか。
副社長に就任した当時は能登の震災の応急的な復旧から本格的な復旧に移るタイミングでした。それ以前から設備系の責任者として震災への対応を行っていたこともあり、副社長就任に際しては震災の復旧に気持ちを新たにして取り組みました。また、その時期は2024年度の事業計画が社内で策定されたばかりで、私たちNTT西日本グループにとっては非常に厳しい経営環境になる見通しであったことから背筋が伸びる思いで、この大変な時代を、責任を持って乗り越えていこうと考えていました。
さて、私は主に設備本部を所掌していますが、NTT西日本約5万人の社員のうち3割の約1万5000人が設備関連分野に所属しており、各自が「つなぎ続けるマインド」を持って、非常に前向きに仕事をとらえて尽力し、スムーズに仕事を進めています。ご存じのとおり、能登では2024年9月の豪雨により、震災から復旧しつつある設備が、土砂により流されてしまうという事態に見舞われましたが、それでも社員は意欲を切らさずに復旧に向けて頑張ってくれました。

前向きに臨まれる素晴らしい布陣ですね。西日本の設備分野について現状を教えていただけますか。
NTT西日本が設立された当初は、固定電話サービスを中心とした事業展開をしており、通信ネットワークは加入者交換機を中心とした所内設備、電話サービス等をお客さまのご自宅まで届けるメタルケーブルを主たる設備とし、これらの設備を収容する通信ビルや地下管路や電柱等の線路敷設基盤等を保有・維持してきました。
一方で1980年代前半に日本でインターネットサービスが登場し、ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)やFTTH(Fiber To The Home)等のブロードバンドアクセス回線の登場によりインターネットが普及してきました。これに伴い、私たちは固定電話からインターネット接続へというサービスの変化に合わせて、アクセス系光ファイバ網やIP電話サービスを提供するNGN(Next Generation Network)を構成する地域IP網の整備を進めてきました。現在は光アクセスサービスの需要は一巡し、固定電話サービスもひかり電話サービスへと移行してきました。併せて、電話サービスの中継網もNGNを使う方式へすべて移行し、落ち着いたところです。
また、携帯電話が広く普及したことで固定電話の加入者数が減少しており、本来であればこれに合わせてメタル系設備量のダウンサイジングを図りたいところです。一方で、固定電話サービスの光系サービスへの移行は一段落しているものの、従来のメタルケーブルは利用され続けているため、光・IP設備との二重設備状況が続いており、光・メタル系トータルの設備量は増加傾向にあります。さらに、NGNを用いたサービスの提供開始から約20年が経過し、各種装置類の更改時期を迎えているというのが現状です。こうした課題に対応していくため、さらなるネットワークの高速化、高機能化や経済化、シンプル化、そして永続的な活用に向けてさまざまな取り組みが必要になっています。
主体的に“考動”し課題を解決する力を磨く
設備も経営も大きな転換期を迎えているのですね。
転換期における今後の取り組みについて、社員と相談しながら、「過去のサービスと設備の縮退」「将来に向けた新たなチャレンジを支える設備づくり」「ベースとしての通信基盤の維持・強化」という大きく3つの柱を立てました。
この3つ柱の背景としてNTT法改正が大きな潮目と考えています。業務規制の見直しなどに合わせて、NTTグループ全体最適となるかたちでのAPN(All-Photonics Network)県間通信提供や、無線サービスを用いることで、メタル設備の縮退を加速することが可能となります。また、私たちは、サービスを提供する30府県にそれぞれ支店を置き、設備分野においては、NTTフィールドテクノの拠点も整備しているように「地域密着で業務を行っている」ことが強みになっています。これらの強みを活かすためにも、この機会に改めて「現場力の継承とアップデート」に取り組みます。
これら3つの柱について具体的には次のとおり進めていくつもりです。
「過去のサービスと設備の縮退」については、固定電話、STM(Synchronous Transfer Mode)専用線などのサービストランスファーとそれに伴うメタルケーブルの撤去・縮退を展開します。メタルケーブルの縮退は2035年までの10年間で完遂することをめざしているものの、固定電話の600万加入をはじめ、いまだ多くのユーザにメタルケーブルを使用したサービスをご利用いただいていますから、そのトランスファーは困難が予想されます。
「将来に向けた新たなチャレンジを支える設備づくり」については、10Gbit/sのインターネット接続サービス「フレッツ光クロス」、企業向けの高速・大容量、高信頼のネットワークサービス「Interconnected WAN」のさらなる拡大と、それに合わせたネットワークの増強、更改、シンプル化、およびAPN等IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)技術の導入とサービス化、ハイパースケーラ等向けデータセンタ間接続のケーブリングビジネス、NTT西日本のアセットを活用した社会インフラの点検効率化等に関するインフラビジネスの拡大をめざします。さらに、地域密着で、私たちだけではなく、産業全体をもっと盛り上げていきたいと考えていますから、IOWN等の最新技術を使って、地方でもいろいろな産業が育っていくようなネットワークを将来に向けてつくりたいと考えています。
なお、IOWNの技術については、2024年12月からサービスを開始している「All-Photonics Connect powerd by IOWN(All-Photonics Connect)」を大阪・関西万博において来場者の皆様に体感していただきます。「All-Photonics Connect」は高速・大容量・低遅延の回線をより広く活用したいとの市場ニーズにおこたえするため、APNサービスである「APN IOWN1.0」提供後のご意見とNTTグループの研究開発成果を踏まえ、お客さまの利便性向上とさらなるユースケースを創出する観点から、NTT東日本およびNTT西日本が提供するもので、ユーザ拠点間の帯域保証型通信としては世界最高水準の最大800Gbit/sの帯域対応と、提供インタフェースとして、イーサネット(400GBASE-FR4/LR4等)対応を実施しています。
ところで、日本の社会インフラを取り巻く環境として、課題となっているのが設備の老朽化や労働人口の減少です。私たちは社会インフラを支える企業として、インフラ設備点検等における自社の技術を通信以外のほかのインフラ企業にも展開します。また、グローバル市場も視野に入れてドローン撮影により設備点検を効率化し、MMS(Mobile Mapping System)による路面等の診断等のビジネスを独自AI基盤である「Audin AI」というサービスを活用して拡大します。
「ベースとしての通信基盤の維持・強化」については、100年利用を見据えた通信ビル利活用等、さまざまなサービスの提供基盤である通信ビルや通信線路敷設基盤(とう道、管路、電柱)などを維持、管理、活用します。これらを着実に実行するため、「現場力の継承とアップデート」を通じて「主体的に“考動”し課題を解決する力」を磨いて、事業運営推進の原動力としていきます。現場力の継承に向けては知見を引き継ぎ、技術や折衝する力を磨き上げていきます。

設備分野の仕事は重要な役割を担っているのですね。
私たちが担っている通信は日本経済の「神経系」にあたり、非常に重要であると考えています。グローバルな競争力が低下している、GDPが下がっているといわれますが、日本にはやはり優れた技術があり、技術者がいます。こうした技術や技術者が、「神経系」である非常に高い品質の通信ネットワークを活用していくことで、日本全体が再び成長できると考えており、そのための下支えをしていきたいですね。
ところで、一般の方が目にする設備の仕事は電柱の工事や、光の回線の開通作業などかもしれませんが、それだけではなく地下の通信網や前述の通信ビルの運用等も仕事の範疇です。鉄道のオペレーションセンタの様子をニュース等でご覧になったことがあるかもしれませんが、私たちも同様に全国のネットワークの運用状況を監視して故障やトラブルに備えています。いわば縁の下の力持ちのような仕事です。しかも、こうしたネットワークを支えるインフラは1日では出来上がりませんから、中長期的な視野を持って、技術を選択する難しさも抱えながら通信が途切れないよう知恵を絞って着実にこれを遂行しています。特に、NTT西日本のエリアには沖縄や長崎、瀬戸内海等を中心に島しょ部が多く、こうした海に囲まれた地域にもさまざまな産業がありますが、私たちはそれらを「つなぎ続けるマインド」でしっかりとつなぎ、地域が地域らしさを発揮して発展していく後押しをしたいのです。これまでもさまざまなお客さまの要望におこたえしてきましたし、これからも新しいことに積極的にチャレンジしてお客さまの要望におこたえしていくことが私たちNTT西日本の歴史なのです。
コミュニケーションのパイプラインを詰まらせない
入社してからの歩みとトップとしての心構えをお聞かせいただけますか。
学生時代からインフラ設備の仕事に興味があり、NTTに入社すれば全国の通信インフラの仕事ができると期待して1992年に入社し、2025年で34年目を迎えました。最初に配属された淀川支店(当時)で通信ケーブルの保守点検業務を主に担当し、その後設備投資計画、経営企画、技術戦略と設備に関する仕事を中心に携わってきました。副社長となって設備全体を見る仕事に就き、日々その楽しさを実感しています。もちろん、災害時の対応や健全な経営を維持すること等、責任の重さを実感しています。
さて、入社3年目の関西支社設備企画部(当時)勤務時代に阪神・淡路大震災が発生し、現場に近い組織で復旧に向けたさまざまな業務を経験しました。そして、2024年の能登半島地震は設備本部長として復旧の指揮にあたりました。このような経験を踏まえて、巨大地震や大規模災害の前には、いつの時代も、何人も無力だと感じます。しかし、それを乗り越えるのが人であり、社会であり、組織だと私は考えています。そのうえで、耐震補強や津波対策、これらを支える技術開発、対応方法のマニュアル化、組織づくり、訓練等と、私たちが今できることはたくさんあります。また、いざ災害が発生すれば時代のニーズに合わせた柔軟な対応が必要です。これらへの対応方針を決めて実行するのがリーダーの役割だと考えています。加えて、リーダーとして危機管理においては冷静に対応することに努めています。
役員となって3年目に大きなインシデント等がありました。ネットワークが大規模な故障を起こして、多くのお客さまに迷惑をかけてしまったことです。こうしたときに陣頭指揮を執る私が舞い上がってしまってはスタッフが動けなくなってしまいますから、仮に動揺等で内心穏やかではなかったとしても、努めて冷静にスタッフの声に耳を傾け、意思決定をしています。仕事は1人でできることには限界があり、特に災害や故障の対応は、1人ではなく総力戦で対峙しなければなりません。こうしたときにこそ、リーダーはスタッフの声に対する傾聴が必要になるのです。ただ、これは非常時に限った話ではないため、日常においても社員の声への傾聴を心掛けています。ありがたいことに、社員の皆さんは各所で経験を積んできたスタッフばかりですから、間違った案はほぼ出てきません。私は壁をつくらずにそれらを集約して自分の意見をスタッフに正直に伝えることを心掛けています。
また、副社長は社長とは担う役割が違います。経営者としての最終的な意思決定を担うのが社長ですが、専門領域に応じて社長の意思決定に必要な知見を補完する立場が副社長ともいえます。現実的にはその領域・分野を副社長が委任されることになるのですが、委任された領域・分野に社長と同等の責任を持って臨むことが仕事ととらえ、だからこそ社長に対しても率直な意見を包み隠さず伝え、なおかつ、社員とトップのパイプラインが詰まらないように意識してコミュニケーションを図っています。

最後に皆様へのメッセージをお願いします。
まず、お客さまにお伝えしたいことから申し上げます。繰り返しになりますが、設備分野は日本の通信のもっともベースとなるところであり、経済の「神経系」を担っていると思っています。いろいろな要望もいただきたいですし、私たちもそれにおこたえしていきます。私たちの技術や設備をご活用いただき、日本がますます活性化するように、共に頑張っていきたいと考えています。
続いて、パートナーの皆様。新しい技術をすぐ導入してほしい等のご要望にこたえることが即座にできないケースも多々あるかと思います。これらに対して私たちは全力で取り組んでいきますが、皆様のご理解とご協力が必要になってきます。こうした局面では、お客さまと一緒に成長していきたいということが私たちの思いであると受け止めていただき、ぜひ一緒に前進していきましょう。
最後に社員の皆さん。NTT西日本グループはNTTグループの中でも厳しい経営環境下にあると思います。ただ、これまでも、さまざまなアイデアで次々と新しいチャレンジをしてきました。このマインドは絶対に忘れずに、NTTグループの中でもNTT西日本が、というよりも日本企業の中でも、NTT西日本がもっとも面白い企業グループだといわれるように成長していきましょう。
(インタビュー:外川智恵/撮影:大野真也)
インタビューを終えて

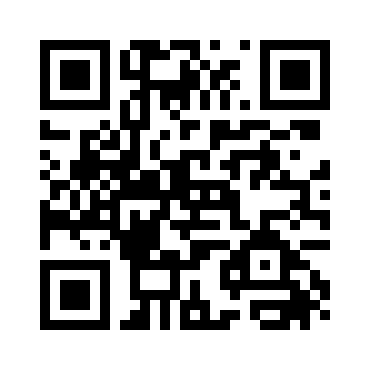




多くのトップが趣味にされていることでも、切り口や楽しみ方に個性が溢れ、意外な一面を知る機会をいただきます。桂副社長にもご趣味を伺いましたところ、ゴルフと野球とお答えくださいました。中でも、野球について詳しく伺いましたところ、桂副社長は大学時代、準硬式野球部でキャッチャーをお務めになられていたそうです。グラウンドに出れば、プレーしている選手に対してコーチや監督の代わりともなる役割を務める、チームの要となるポジションを担われていた桂副社長。「キャッチャーとして全体を見る力や配球の選択はビジネスにも非常に有効かと思います」と、誌面の彩を気遣ってお答えくださいました。
そんな桂副社長は「常に穏やかです」と社員の皆さんはおっしゃいます。実は、先祖代々続く氏神様の神職もしていらっしゃるとのこと。「寺社は、地域コミュニティの一角を成し、日本の伝統や文化、行事や風習の基となっています。神社神道には、伝統的な形式美や様式美があり、祭祀の作法などは厳密に定められているのですよ。一方で、時代に合わせた変化も必要で、祈祷内容や授与品は時代により移り変わります。このような伝統の維持と変化への対応という姿勢は、経営にも活かすべきと考えているのです」と桂副社長。
心を落ち着かせ決意を新たにする意味で、1日の仕事の前の神棚拝礼は欠かさないように努めていらっしゃるそうです。あらゆることから教訓を導き社会に還元されるご姿勢に学ばせていただいたひと時でした。