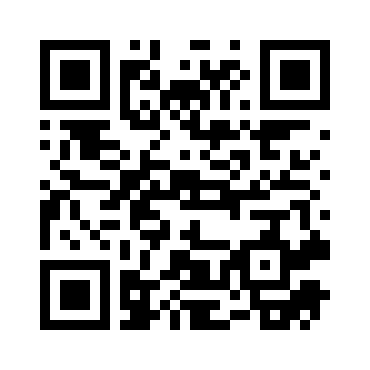2025年7月号
特別企画
技術の本質を徹底して追求。パッションは好きなことにしか注げないものである

元日本電信電話株式会社CSSO(Chief Standardization Strategy Officer)で、現在国際電気通信連合(ITU:International Telecommunication Union)電気通信標準化局長の尾上誠蔵氏がIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)の2025 IEEE Jagadish Chandra Bose Medal in Wireless Communicationsを受賞しました。本賞は分野ごとに21種あるIEEE Medalsの1つで、最高位のIEEE Medal of Honorに次ぐ賞の1つとして、2025年に新設されました。この受賞を記念して、受賞理由の1つであり、4G(第4世代移動通信システム)に向けたLTE(Long Term Evolution)のコンセプトを提唱し、「LTEの父」と呼ばれる尾上誠蔵氏にお話を伺いました。
尾上 誠蔵(おのえ せいぞう)
LTEの父、世界的な影響力を持つ無線通信技術への貢献を称える新設賞を受賞
■2025 IEEE Jagadish Chandra Bose Medal in Wireless Communicationsの受賞、おめでとうございます。東京で華やかな授賞式が開かれたと伺いましたが、いかがでしたか。
ありがとうございます。授賞式は豪華ゲストを迎えたガラディナーの一環として行われ、私だけではなく他のIEEE Awardsの受賞者の方々への贈賞も行われました。表彰される際、受賞者を紹介する短いビデオが会場で放映されます。私はそのビデオを当日初めて観ましたが、私が提出した写真などを上手く構成してくださったと感心しつつ、初めて見たと言ったら、皆さん笑っていらっしゃいました。
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)からの正式な通知は電子メールによるもので、2024年の暮れに秘書から「IEEEから連絡がないか」と聞かれたので、確認したところ、その通知メールをゴミ箱から見つけました。正式な通知を確認して、改めて今回の受賞を実感した次第です。
さて、私はこれまで2014年に文部科学大臣表彰 科学技術分野の功労者表彰、2018年に紫綬褒章等を頂戴しました。こうした賞をいただくことは嬉しいことなのですが、今回の賞は米国の学会とはいえIEEEからのものであり、グローバルで認めていただけたことに嬉しさもひとしおです。

■本賞は世界最高の同業者表彰プログラムであるIEEE Awards Programにおいて、世界的に大きな影響を与え、無線通信技術の進歩に極めて重要な貢献をした、卓越したリーダーや先見者に授与されると伺いました。尾上さんはその記念すべき初の受賞者ですね。改めてIEEEと本賞、そして授賞理由を教えていただけますでしょうか。
IEEEは、世界最大の技術専門組織で、人類のために技術を発展させることを目的とした公益団体です。航空宇宙システム、コンピュータ、電気通信から、生体医工学、電力、家電に至るまで、幅広い領域で信頼される機関で、出版物、会議、技術標準、専門的・教育的活動を通じて、高い評価を得ています。
そして、IEEE Awards Programは、1世紀以上にわたり、科学、技術、工学の進歩に貢献した人物を表彰するプログラムで、IEEEが関心を寄せる21種の分野における貢献を表彰しています。今回、私がいただいたJagadish Chandra Bose Medal in Wireless Communications賞はその中で無線通信技術への貢献をした人物に授与されるもので、2025年に新設されました。無線通信における技術的貢献、新技術の実装、標準化、または商業化、専門分野および、または社会への影響、目標を達成するためのリーダーシップ、これまでの実績、および出版物や特許などが評価の対象です。私は、受賞理由として、3G(第3世代移動通信システム)および4G(第4世代移動通信システム)の研究開発および国際標準化を世界的に主導し、世界的な普及に貢献したと評されました。
表彰の対象は3Gと4Gであり、セル検索アルゴリズムの開発など技術的貢献も強調されていますが、私にとって、もっとも幸運であり誇りに思うのは、移動通信の1G(第1世代移動通信システム)から5G(第5世代移動通信システム)すべての世代にかかわることができ、現在も6G(第6世代移動通信システム)を仕事の対象にしているということです。このことは受賞のスピーチでも述べたのですが、本当にそう思います。振り返ってみれば、世界統一標準をめざした3G、そしてそれが実現した4Gという、標準化の観点でもっとも重要な時期にあった移動通信世代が対象になったのは大変幸運だったと感じています。
私にとって標準化はシステム開発の一環として取り組んでいたことです。標準化は単なるツールですが、それは非常に重要で強力な手段であり、私はそれを活かすことに努めてきました。技術を標準仕様に盛り込むための議論ではなく、最終的にはその技術が広く普及し、世の中の役に立つことを見据えた標準化こそが重要だと考えてきました。今回の受賞はこのような信条や活動をご理解いただいたのだと思います。
標準化においてもっとも重要なタイミング3G、4G時代の貢献が高く評価された
■3G、4Gの研究開発が表彰対象になっていますが、移動通信システムの技術は各世代どのような特徴があるのでしょうか。
私は、1982年に電電公社に入社して研究所に配属されたときは、日本で世界初の自動車電話サービス開始後3年目で、契約者数がさほど多くない時期にもかかわらず、大容量方式の開発が大きなテーマでした。1Gは、アナログ方式の移動通信の黎明期であり、各国で異なる規格が乱立していました。自動車電話から始まり、端末の小型化が進むと携帯電話システムに進化しました。2Gでは、欧州が統一標準にしたこともあり、規格の数は少なくなりましたが、日米欧で異なる方式になりました。日米は多少のハーモナイズの努力があり、3チャネルTDMA(Time Division Multiple Access)は共通ですが互換性のない方式になりました。日本の方式はPDC(Personal Digital Cellular)と呼ばれ、音声もデジタル多重化され2400 kbit/sのデータ通信やファクシミリ通信が可能となりました。1999年にはiモードも登場し、爆発的普及拡大期を迎えました。世界的にはヨーロッパ発のGSM(Global System for Mobile Communications)が地域を越えて世界に広く普及しました。
3Gにおいては世界統一インタフェースをめざして、ITU-R(International Telecommunication Union - Radiocommunication Sector) で議論して、2Mbit/sの通信を可能とするといった目標を含むIMT-2000ビジョン勧告をつくり上げました。各国地域から提案されましたが、日本では早い段階でNTTドコモが推進していたW-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)方式が選定され、最終的にIMT(International Mobile Telecommunication)-2000の1つに採用されました。W-CDMAは、後にさらなる進化形のHSPA(High Speed Packet Access)が導入され、2Mbit/sを超えて最大14.4Mbit/sのパケット通信が可能となります。
3Gの市場展開が始まった当時、NTTドコモでは4Gの研究が着実に進んでいて、2002〜2003年には100Mbit/s、さらに研究レベルでは1Gbit/sというデータ伝送を実現していました。その一方で、3Gのビジネスは契約者数が思うように伸びず、決して順調とはいえない状況の中で4Gの研究成果を市場に出すことは極めて困難に思われました。ここで学んだ教訓は世代間のスムーズな進化パスが重要ということです。そこで、「スーパー3Gコンセプト」を提唱しました。これは、まず3Gを発展させて、その上に4Gを築き上げようというコンセプトで、そのまず発展させた3Gをスーパー3Gと呼んだのです。これは全く概念的なもので、実際は4G用に開発したOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:直交周波数分割多重)を採用することを狙っていました。この標準化はロングタームエボリューション(LTE)として進められました。LTEでは、複数のアンテナを使ってデータの送受信を同時に行うことで通信速度を向上させる、MIMO(Multiple Input Multiple Output)が採用されています。さらにその後には、音声デジタル信号をパケット通信により伝送する、VoLTE(Voice over LTE)が採用され、クリアな音質の新しい音声コーデックの採用が可能となりました。

■各国・地域の思惑が交錯する国際標準化の舞台ではどのようなご苦労があったのでしょうか。思い出深いエピソード等をお聞かせください。
3Gについては、世界統一標準をめざしたこともあり、各国のプレイヤが自分の技術を国際標準にしようと熾烈な論争になりました。各国地域での選定、最終的に世界レベルへの統合と、段階を追って議論が過熱しました。
欧州では標準方式の対象として5つの候補があり、そのうちの1つがW-CDMAです。欧州の標準化団体ETSI(European Telecommunications Standards Institute)の中では、TD(Time Division)-CDMAとの間で1年間ほど激しく議論が展開されていました。これは欧州での議論ですが、日本はNTTドコモが推進したW-CDMAに決めていたため、NTTドコモとしても深くかかわり欧州出張が増えた時期です。ある欧州オペレータとのミーティングでコアネットワークプロトコルはGSMとする前提で、無線アクセスはW-CDMAする方向性に合意するなど進展がありました。それが1998年1月の会合において、W-CDMAを基本として一部にTD-CDMAを取り入れることで欧州提案が決定しました。この過程ではTD-CDMAを推すあるベンダとも個別の技術論争をしましたが、後に、その論争相手の技術者と共著でIEEE Communication Magazineに投稿するという関係にもなりました。
米国ではW-CDMAとは異なるCDMA2000を主要プレイヤが推進していました。日欧対米国という構図にとらえられますが厳密には国地域間の戦いでなく、W-CDMA対CDMA2000の論争であり個々ベンダやオペレータのプレイヤどうしの議論です。これが世界統一標準をめざす最後の段階です。単なる技術論争だけでなく、標準化とはある意味背中合わせの関係にある特許等のIPR(Intellectual Property Right)の扱いに関する議論まで展開され、標準化の進展が危うくなり、当時は未来永劫3Gの国際標準仕様ができないのではないかと思ったほどでした。技術的に両方式のハーモナイズを試みた数多くの取り組みがなされましたが、失敗の連続でした。最終的にはオペレータハーモナイゼーショングループ(OHG)で議論したハーモナイゼーション提案が合意されました。共通性を高めるために一部のパラメータを変更するものですが、結局両方式を互いに認め、相互運用のためのエクステンションを定義するという案で、本当の意味での唯一の世界統一標準ではありませんでした。IPRの問題もベンダどうしの合意で解決し、OHGのハーモナイズ案をベースに標準化が進むことになりました。NTTドコモは2001年3G商用開始に向けてシステム開発を進めていましたが、最終段階でのキーパラメータの変更や標準化の遅延は商用システム開発に大きく影響し、それはそれで大変だったのです。
4Gにおいても、前述のように、3Gで学んだ教訓である、次世代へのスムーズな進化パスが重要でした。先ほどNTTドコモのビジネス上の話をしましたが、実際、欧州を含むオペレータは3Gへの莫大な投資の後、次世代への投資を躊躇し、4Gの標準化に消極的でした。4Gの標準化は標準化を開始しようとする仲間づくりから始まりました。標準化に強い影響力を持つベンダとの個別ミーティングから始め、次第にオペレータを含むマルチラテラルミーティングで標準化開始の機運を高めました。これらのベンダには、対CDMA2000の論争相手だったベンダも含まれており、技術的に先進的で尊敬すべき技術者が多くいると認めていました。まさに昨日の敵は今日の友のごとく、協力関係を持って進みました。
2004年12月の3GPP(Third Generation Partnership Project)の会合で検討を始めることが合意され、私が取材を受けた内容が、大晦日の日経新聞朝刊一面に「スーパー第3世代」と報じられたのを憶えています。3GPPでの検討が進みワークアイテムの略称がロングタームエボリューションから来たLTEだったので、LTEがよく知られるようになりました。
一方、CDMA2000側もその発展形のUMB(Ultra Mobile Broadband)の標準化を進めていました。CDMA2000は第2世代ととらえられているcdmaOneからのアップグレードが容易でその普及は早かったのですが、W-CDMAはGSMコアネットワークを基盤にしており、2Gで世界的に広く普及したGSMを採用するオペレータが自然に導入するので、W-CDMA契約者数が標準化後何年も経ってから逆転することが明確になりました。この状況で、主要なCDMA2000オペレータがその発展形のUMBでなく、LTEを導入することを発表したため、LTEが唯一の統一世界標準になることが明確になりました。私は後に、このCDMA2000オペレータにおいてこの判断をしたといわれる当時のCTO(Chief Technical Officer)に会う機会があり、感謝の意を伝えました。標準は標準化の場で決まるとは限らず、このように市場が標準を決めることがあります。市場動向を読む重要性とGSMの成功に乗る判断の正しさが10年後に証明されました。
技術標準の普及のための標準化を 進め,技術が安価になり、さらに 技術が広がるという世界づくり
■これまでの各世代の移動通信システムの開発者、およびITU電気通信標準化局長という現在のポジションから標準化や研究開発を眺めたとき、今後のBeyond 5G/6G技術発展にどのような思いをお持ちですか。
私は、「偶数世代のみ大成功の法則」を見出したように、分析を基に将来のトレンドを読むことを楽しんでいます。技術の動向や開発の傾向を、なぜこうなるのだろうと常に意識・分析して眺めています。意外なメッセージで人の注意を引くための意図もありますが、同時に重要なメッセージを発信できます。
その視点で、移動通信の技術発展を眺めたときにこの偶数世代の法則がこの先成り立たなくなると気付きました。これは直近のインタビューで経済部の記者からの「なぜ(移動通信システムは)世代交代をするのか」という素朴な疑問を呈された際のことです。これまで約10年ごとに新しい世代が登場してきました。3度も4度もそれが起こるとこれからも10年ごとに新しい世代が出てくると、自然にそう考えてしまいます。4Gまでは、世代交代のたびにアナログFMからデジタルTDMAに、さらにW-CDMA、OFDMAへと、新しい無線アクセス技術が登場してきました。しかし5G以降は、新しいコンセプトに基づく技術というよりも、既存技術の延長といえます。私はこれを、例えばアンテナ数を増やすといった「力業の技術」と呼んでいました。このように技術進化の観点から5G以降は様相が変わっています。さらに標準化の観点でも、世界統一標準に至る4Gまでと、それ以降の5Gでは局面が変わっています。これらの変化を踏まえると、これまでの「移動通信世代の法則」は、5G以降への適用が危うくなるかもと最近考えるようになりました。
5Gの場合は、他業界からも注目を集めることで業界間のコラボが生まれる良い面がある一方で、過度にマーケティングツールとして使われてしまって市場に混乱を来たす悪い面が出てしまったと思います。
マーケティング、ブランディングに惑わされることなく技術の本質を見極めて、次の10年、次の世代でどのタイミングでどの技術を普及させるかをしっかりと考えるのが重要です。ITUにおける現職の立場からすれば、まだ世界人口の3分の1はインターネットに未接続で、いまだに2Gに頼っている多くの国があることにも目を向けなければなりません。必要以上に早い世代交代はこうした地域との格差を広げるリスクがあります。開発途上国にとっても技術先進国にとっても世界全体のエコシステムが最適になる世代進化を追求していく必要があります。

■最後に今後の抱負と、次世代を担うNTT内外の研究者・技術者へのメッセージをいただけますでしょうか。
NTTの研究所に入所した当時は興味本位で研究開発に取り組んだこともありましたが結果的にそれらは採用されず、研究所はそれらを本当に役に立つものではなかったと、健全な判断をしたのだと今になって思います。そうした経験も含め、私は常に技術への情熱、すなわち“パッション”を持って仕事に取り組んできました。
当時の私は研究開発に夢中で、そのころの私からしたら今回の受賞も、今日のポジションに就くことも想像もつかなかったはずです。本当に私は技術を前に進めること、性能の向上ばかりを追い求めていました。一般に技術進化は人々の生活や社会の幸せにつながりますが、過度なマーケティングのための技術、技術の本質に根差さない進化は世界全体に悪い影響を与えます。今から思うとこの過去の私の姿勢や業績は世界のエコシステムにプラスに働いたか今の立場で検証が必要ですが、おそらく間違いはなく、技術進化は社会を幸せにすることに貢献したのではないかと思います。
開発者、研究者の皆さんは、興味が持てる、情熱が注げる技術開発に集中するのが一番です。その一方で、世界中の人の役に立つという視点も忘れないでほしいと今の立場で思います。世界中にはさまざまな人がいて、さまざまな文化的・経済的背景をもって生活しています。こういった人たちすべてに役に立つということは、その技術が世界中どこでも使えるということにほかなりません。そのための重要な役割を果たすのが国際標準なのです。だからこそ、国際標準化の価値を意識して技術開発を進めていただきたいのです。これを進めていくためには、どうぞパッションを大切にしてください。
最後に、現職のITU電気通信標準化局長のポジションは選挙によって選出されます。現在はその際に掲げた技術標準を世界に広げるというコミットメントの実現に向け一生懸命実行しています。標準を開発するだけでなく、それが広く普及して初めて国際標準化の価値が出ると考えています。今後も技術標準の普及のための国際標準化をしっかりと行い、それによってサービスが安価になり、さらに技術が普及し、人々や社会の役に立つという世界づくりに努めていきます。