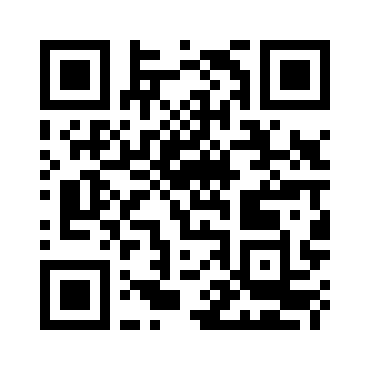2025年8月号
特集2
瞳孔径から読み解く心の動き

鈴木 雄太
NTTコミュニケーション科学基礎研究所
人間情報研究部
感覚表現研究グループ
私たちは、外界から感覚器をとおしてさまざまな情報を得ています。例えば視覚では、目から入った光が網膜を経て脳に伝えられて処理されることで、世界を「見る」という体験が成り立っています。視覚科学の発展により、そのメカニズムは徐々に明らかにされてきましたが、いまだ十分に解明されていない機能や神経の仕組みが残されています。NTTコミュニケーション科学基礎研究所ではAI(人工知能)を含めた多様なアプローチを活用しながら、心まで伝わる深いコミュニケーションを支える人間の知覚・認知とその背後にある脳のメカニズムを明らかにすることをめざして、日々研究を進めています。
私たちは、瞳孔の大きさなどの目から得られる生体信号をとおして、脳の働きを読み解こうとする研究を行っています。瞳孔径は周囲の明るさに応じて変化し、同時に感情や注意、判断といった、さまざまな心の状態を反映して変化していることが知られています。こうした目の情報を使った研究を私たちは「アイメトリクス研究」と呼んでいます。近年では、高性能な小型センサ技術の進展により、メガネ型のデバイスを装着するだけで視線や瞳孔径の情報を簡便に取得できるようになってきました。
私たちのアイメトリクス研究では、瞳孔径の変化を通じて人間の認知過程を読み取る「マインドリーディング」に取り組んでいます。私がこれまでに行った研究では、2つの音が交互に繰り返される音列に対して、聞こえ方が時間とともに自然に切り替わる現象(知覚交代)に注目し、知覚交代のタイミングで瞳孔がどのように変化するかを調べました。聞こえ方の変化は本人にしか分からない主観的な体験ですが、私たちは知覚交代が頻繁に生じる数10秒前から、すでに瞳孔径が大きくなっていることを発見しました。つまり、知覚交代の前から、脳の中ではその準備が進んでいて、その活動が瞳孔径に反映されていると考えられます。このように、瞳孔径をとおして脳における情報処理の状態(内部状態)を知ることによって、音の聞こえ方に限らず、これから起こる意識的な体験を予想したり、自分がどのような状態であるかを事前に知ることによって、その後の行動を決めたりするような手掛かりが得られるかもしれません。
また、瞳孔径から脳活動を読み取るといったアプローチに加えて、光を使って集中力の持続や眠気の軽減を促すといった能動的な介入を行う研究を始めています。私たちがこの研究で注目しているのは、内因性光感受性網膜神経節細胞(ipRGC)です。ipRGCは、従来知られていた錐体・桿体細胞に次ぐ「第3の光受容細胞」とも呼ばれ、短波長光(青緑色)に対してよく反応し、網膜に存在しながら、概日リズムや睡眠といった非視覚的な生理機能に関与することが知られています。近年の研究ではipRGCの刺激に伴い、脳の前頭前野を含めたさまざまな領域で活性がみられることが明らかになってきました。ipRGCは色を感じる錐体とは独立に光を感受するため、視覚的には同じ色に見える光でも、その波長成分を制御することでipRGCへの活性強度だけを変えることが可能です。私たちの最近の研究では、作業記憶課題の実施中にipRGCを活性させる光を背景に提示することで、課題のパフォーマンスが向上することが確認されました。さらに、課題中の主観的な疲労感や眠気の軽減がみられることを発見しました。この知見をうまく活用すれば、オフィスや教育環境における照明のipRGC活性をうまく制御することによって、効率良く作業ができる環境づくりにつながるかもしれません。また、他の生体情報と組み合わせてうまくセンシングと介入を行うことで、より適切な睡眠を促す仕組みなどに応用できる可能性もあります。
アイメトリクス研究によって多くの脳のメカニズムが明らかにされてきましたが、いまだに解き明かされていない課題も数多く残されています。アイメトリクス研究が進むことで、主観的な体験をリアルタイムに他者と共有したり、自分でも気付いていない内的な状態をフィードバックするような技術や適切な介入技術の実現により、人と人とがより深く理解し合い、豊かなコミュニケーションを築いていける未来に貢献できることを願っています。