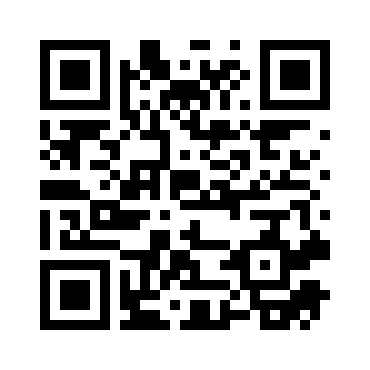2025年10月号
特集1 主役登場
エネルギーとICTの最適融合により持続可能な未来を切り拓く

マハムド ファーハン
NTT宇宙環境エネルギー研究所
環境負荷ゼロ研究プロジェクト 主任研究員
カーボンニュートラルの実現は地球環境だけでなく、経済や社会の持続性にもかかわる重要課題となっています。化石燃料の消費削減に向け各国では様々な政策を進めており、特に再生可能エネルギー(再エネ)の導入拡大が急務となっています。
一方で、生成AI(人工知能)の急速な普及により、データセンタ(DC)の電力需要は急増しています。NTTグループでも、環境エネルギービジョン「NTT Green Innovation toward 2040」のもと、2030年にDCのカーボンニュートラルを掲げ、全社で取り組みを進めています。この中でも、いかに再エネを有効活用するかが重要なテーマとなっています。
こうした流れの中で注目されているのが、エネルギー(ワット)と情報通信(ビット)を高度に統合する「ワット・ビット連携」という概念です。電力とICTの融合により、DCの電力需要と再エネ供給を最適にマッチングさせ、持続可能な社会基盤の構築をめざす取り組みです。私が所属するNTT宇宙環境エネルギー研究所では、環境負荷削減と環境適応に関する研究開発を進めており、その中で私はワット・ビット連携を通じた再エネ利用量の最大化に取り組んでいます。
再エネは地域や時間帯によって発電量が大きく変動する特性があり、安定的かつ効率的に活用するには、その変動性に応じた需要家側の柔軟な運用の実現が課題です。これを解決するため、私たちはソフト/ハードの2つのアプローチを軸に取り組んでいます。1つは、再エネの発電状況に応じてDCの処理負荷(WL:ワークロード)や蓄電池の充放電を柔軟に制御する「エネルギー・ICTリソース統合制御技術」というソフトウェア的アプローチです。もう1つは、再エネ活用に適した場所にDCを設置するための「DC配置最適化技術」というハードウェア的アプローチです。
エネルギー・ICTリソース統合制御技術は、再エネ電力が不足する地域のDCから、余剰が見込まれる地域のDCへWLを移動させるとともに、再エネの余剰タイミングで蓄電池に充電した電力を不足時に放電することで、各地域における再エネ利用率の向上を実現する技術です。一見シンプルですが、実現には電力需要・発電量の高精度予測や最適化アルゴリズム、仮想環境での制御実行など、多様な技術要素が必要で、その連携の難しさを実感しています。私のチームでは予測結果を基に、DCごとのWL量や蓄電池の充放電量といったエネルギー需要を最適化するアルゴリズムの設計・開発を担当しています。社会実装に向けては、他の技術要素を担う研究所や事業会社と密に連携し、実証実験や共通基盤の開発などを通じて、実現性の検証も進めています。特に、効果をより拡大するためには、電力事業者や大手DC事業者などとの社外連携が重要で、各社と合同議論の場で問題提起するなど、巻き込み型の推進を意識しています。
DC配置最適化技術は新設した研究テーマで、DC新設や既存通信ビルのDC化を検討する際に、再エネ発電ポテンシャルや地域別の電力需要、各種コスト、電力系統状況などを総合的に評価し、コストや再エネ利用率等を踏まえてDCの配置を最適化する技術です。インプットデータは多岐にわたるため、それらを広く網羅するには、地域の電力会社や通信事業者、行政機関等との連携を前提としたデータ共有の仕組みづくりが不可欠です。また、評価軸も一律ではなく、目的や優先度によって大きく変動するため、立ち上げ段階から利用者の声を丁寧にヒアリングし、柔軟に条件の切り替えが可能なアルゴリズム設計を進めています。
私はこれまで、無線基地局における電波干渉に関する障害対応や、無線エリアの設計・構築支援といった現場業務に携わる経験も積んできました。近年では、5G(第5世代移動通信システム)の高度化に伴って、基地局が処理するトラフィック量や搭載機器が増加し、基地局当りの電力消費も年々増加しています。こうした背景から、消費電力を抑える「グリーン基地局」の導入も徐々に進んでいます。加えて、無線アクセスネットワークの仮想化(vRAN)に向けた取り組みも活発化しており、基地局の機能が汎用サーバ上のWLとして柔軟に移動できることで、電力需要の分散や再エネの有効活用にもつながる可能性がみえてきました。
現在取り組んでいるワット・ビット連携の技術も、将来的にはDCにとどまらず、こうした無線基地局への適用も視野に入れています。これまで培ってきた無線の知見を活かし、エネルギーと通信を一体で最適化することで、将来的にはネットワークインフラ全体のグリーン化にも貢献していきたいと考えています。