2025年10月号
トップインタビュー
人は宝。社会と社員を照らし続けるトップでありたい

情報通信インフラ関連業務をとおして培った技術力とパートナーの皆様との共創を通じて、設備の老朽化、労働力不足、環境問題、災害対策など、社会のさまざまな課題に挑戦するNTTインフラネット。日本の社会インフラ全体の最適化と持続可能性に大きく貢献する取り組みに注目が集まります。新しい時代における社会インフラの構築・運用を手掛ける上原一郎NTTインフラネット代表取締役社長に事業展開とトップとしてのあり方を伺いました。
NTTインフラネット
代表取締役社長
上原 一郎
PROFILE
1988年NTTに入社。2013年NTTネオメイト代表取締役社長、2017年NTT西日本取締役ビジネス営業本部長、NTTビジネスソリューションズ代表取締役社長、2019年7月NTT西日本代表取締役副社長を経て、2023年6月より現職。
NTTインフラネットが興す「社会インフラ革新」
NTTインフラネットの事業とビジョンについて教えてください。
NTTインフラネットは日本における通信の地下基盤インフラを支える企業として1999年に設立され、約四半世紀にわたり事業を展開してきました。私たちはもともとNTTグループが持っているとう道や地下管路などの通信基盤を管理しています。管路のみでも、その規模は全長で約67万kmにも及び、全国の上水道の総延長並みの長さがあります。
現在、これらの通信基盤を維持・運用する技術・知見を、情報通信分野のみではなく、電力、ガス、水道など、インフラ事業者や自治体の保有する社会インフラに活用していく「ソーシャルインフラ・イノベーション」を推進しています。「ソーシャルインフラ・イノベーション」を事業として展開するにあたり、大きく2つの柱を立てました。1つはインフラエンジニアリング事業で、無電柱化工事や再生可能エネルギー自営線構築などの社会基盤ビジネスにおいて、自治体をはじめとする道路管理者などと連携して設計、工事とこれに伴う各種調整を行います。もう1つはスマートインフラ事業で、デジタルトランスフォーメーション(DX)によってスマートメンテナンスなどのインフラ管理ビジネスや電子地図などの空間マネジメントビジネスを推進します。この2つの事業が両輪として機能していくことで、「ソーシャルインフラ・イノベーション」につながっていきます。
背景として、設備の老朽化、災害リスク、技術者不足、予算不足など、私たちも含め多くのインフラ事業者や自治体が同様の課題を抱えている現状があります。NTTインフラネットは、電力、ガス、水道などの他のインフラ事業者とのコミュニティを形成しており、私たちの基盤設備の運用・維持に関するアプリケーションやリソースのシェアリングによって、共通の課題を解決できるのではないかと考えました。そして、インフラ個々ではなく、社会インフラ全体としての視点から考え、協業することで社会インフラの課題解決に取り組み始めたのです。
情報通信分野のインフラに関する事業はほぼ飽和状態にある中で、「ソーシャルインフラ・イノベーション」として他の分野を含んだアプローチにより、私たちの強みを活かした新たな事業展開につなげることができると考えています。

社会課題を担うNTTスピリットを感じる取り組みですね。順調に進んでいますか。
順調な面と苦戦している面、両方あります。順調な部分としては、「ソーシャルインフラ・イノベーション」について他の事業者や自治体から賛同を得られ、私たちのシステムやリソースのシェアリングがうまく機能し始めていることです。一方で、自治体や事業者によって設備状況・環境が異なり、取り組みがスケールしていない点やDXを推進していくうえで重要となるデータ共有が理想的なかたちにまで至っていない部分もあります。
昨今は都市開発が進み、技術開発のスピードも速くなる中で、現場では、既存のインフラをどう維持・活用していくのか、そして、新しいインフラをどのように構築するのかを検討し、最適化を図っています。例えば、インフラエンジニアリング事業の中でも近年増加している無電柱化工事において、通信や電力の既存設備を有効活用する既存ストック工法を推進することで、工期短縮やコスト削減を達成しています。また、無電柱化工事は電柱を保有する電力会社やガス管を埋設しているガス会社などのインフラ事業者のみならず、周辺住民や警察まで含めた合意調整に時間がかかるのですが、「PFI事業方式」や「包括委託方式」のスキームにより、道路管理者に代わってNTTインフラネットがこれらの調整業務を実施することで、大幅な工期短縮を実現しています。
一方、スマートインフラ事業の代表的な例として、NTTインフラネットは「立会受付Webシステム」を提供しており、多くのインフラ事業者への工事立会の申請をワンストップかつデジタルで受け付けることで、インフラ事業者や自治体の事前調査や調整協議の負担を軽減しています。これまでに60のインフラ事業者がこのシステムを利用し、月約10万件の工事立会を受け付けています。さらに、通信インフラ以外の分野でも、通信インフラを点検する「スマートメンテナンスツール」を下水道インフラに活用して点検を実施していただき、下水道の老朽化と技術者の減少への自治体の対策の1つとなっています。
また、現在、私たちは、経済産業省が中心となって推進している「デジタルライフライン全国総合整備計画」に参画しています。その中で、「インフラ管理DX」プロジェクトは、地下構造物の位置情報を高精度3Dの絶対座標で把握するプロジェクトです。地下構造物の2次元位置情報は過去からGIS(Geographic Information System)やCADによって管理されてきているため、ある程度把握できていますが、地下構造物の3次元モデルの位置情報は整備がされていません。これを高精度に3次元化し、各種インタフェースを統一していくことで、採掘工事の際に掘削機械の操作画面に地下設備の埋設状況を視覚的に表示することで安全性を向上させたり、災害発生時に各インフラの被害状況や復旧情報を集約し、防災アプリの画面に表示することで復旧計画の迅速化を図ることができます。こうした取り組みをとおして、暮らしやすい街の未来を築くことに私たちの技術やノウハウを活かしていきます。
新パーパス「新しい社会のインフラをつくり、次の時代に つなぐ」
NTTインフラネットは順調に成長されていますね。社長就任から2年が経ち、手ごたえを感じていらっしゃいますか。
NTTインフラネットはここ数年、増収増益で成長しています。前述のとおり、これまで私たちの事業はNTTの情報通信に関する仕事が中心でしたが、現在は外部の仕事、特に「ソーシャルインフラ・イノベーション」による社会貢献が主要業務となっています。すでに2年前にNTT向け事業の売上と外部向け事業の売上が逆転し、この傾向が顕著になってきました。この2年間、社員の皆さんにこの新しい方向性を理解してもらい、同じ方向を向いて進んでいくことにやりがいを感じています。
こうしたNTTインフラネットの役割の変化をとらえて、さらなる前進をめざして、パーパスの制定に取り組みました。パーパス制定にあたり、社員から意見をもらい、議論を重ねてきました。こうして制定された新しいパーパスが、「新しい社会のインフラをつくり、次の時代に つなぐ」です。シンプルな言葉ですが、その背景にはさまざまな意味があります。
「新しい社会のインフラ」とは、いうまでもなく単なる情報通信インフラではなく、社会全体のインフラを考えることです。そして、既存のものをそのままつくり変えるのではなく、持続可能なかたちにして、未来に「つなぐ」ことが重要です。そして、インフラというとハードウェアが中心のイメージがありますが、プラットフォームやアプリケーションなどのソフトウェア面、さらには発注方法や工事方法など新しい仕事のやり方や仕組みも含んでいます。
新しいパーパスについて単に文言を共有するだけでなく、社員と一緒に言葉の意味を考え、共通の価値観を醸成していくために、全国の事業部や47都道府県にある支店を回って社員との対話会を開催し、パーパスの意味や意義について対話する機会を設けています。対話会では、現場の「リアル」も踏まえて議論しながら、既存の分野を越えた取り組みについて実例を聞くことがあります。例えば、複数のインフラ事業者にまたがる業務をワンストップで受けたり、通信インフラ点検のノウハウやシステムを他のインフラに活用したり、領域を越えた柔軟な発想による取り組みを聞くととても嬉しいですね。自治体などとの間に築いてきた信頼関係があるからこそ、領域を越えた工夫やチャレンジができているのだと思います。

主体性を持って仕事に臨まれる社員の活躍、嬉しいですね。社員を率いる際に大切にしていることがあれば教えてください。
NTTインフラネットは真面目な会社だと思います。良い意味でNTTグループの設備部門ならではの特徴なのでしょうね。大規模なプロジェクトで完成までに長い期間かかることもあり、基盤系の継承されてきた技術やノウハウを活用し、真摯に仕事に向き合う社員が多いと感じています。
さて、前職のNTT西日本副社長時代は、社長という相談相手がいましたが、社長の立場になると最終的に自分がこの会社の将来を考えなければならないという違いがあります。心のどこかで「自分が最後の砦」、最終意思決定者だという意識が強まりました。こうした実直な社員を率いていくためにも、意思決定の際には実際に仕事をしている人たちの声や考え方を重視します。特に大型プロジェクトは外部とのやり取りが多いので、お客さまの考えや、世の中がどう動いているかを踏まえて判断しています。将来的に会社をどう成長させるかという点も社長として重要なテーマで、現在の事業をベースに選択するのか、全く新たな方向性を考えるのかという難しさもありますが、意思決定の際には「心は熱く、頭は冷静に:Cool head、but warm heart」をモットーに臨みます。志や情熱を持って取り組むことは非常に重要で、うまくいかないと思っても工夫をしながら頑張っていると突破口が見つかることがあるものです。一方で、冷静に考えることも大切だと実感していますから、バランスを取りながら進めています。
新しいプロジェクトに自ら手を挙げて養った情熱。数々の災害対応を経て知った冷静な判断力の重要性
情熱的であり、冷静でありたいというお考え、ご姿勢に至った経歴をお聞かせいただけますか。
私は1988年にNTTに入社しました。ちょうど昭和の最後の年で、バブル経済期に差しかかるころでした。会社も電電公社からNTTに変わって3年という時期で、さまざまな分野で新しいチャレンジが進んでいました。私は設備分野で、光ファイバを全国に展開する仕事からスタートしました。当時はメタルケーブルによる電話サービスが中心だった時代で、光ファイバをどう導入して活用していくかという課題に取り組んでいました。そこでは、光ファイバは高速通信が可能であり、競争力があるという考えの下、NTTが設備を保有してサービスを提供するという設備競争を経験しました。その後、法人営業を経験し、法人や地域のお客さまとのコラボレーションが進み、さまざまなパートナーとして連携していく中で、私たちが保有する設備や人材をどう活用していただくかという視点を大切にしてきました。現在は設備関連の会社に戻ってきましたが、これらの経験を踏まえて、単独の設備を活かすというよりも、インフラ全体をどうしていくかを考えるという観点で仕事に臨んでいます。
NTT入社以来約40年の歩みにおいて、「情熱的であり、冷静である」この考えに至ったきっかけが2つあります。
1つは入社数年後に新しい技術やプロジェクトにかかわる機会があったことです。電電公社からNTTになって新しいことに挑戦する流れの中で、自らが志を持ち手を挙げて、「最新技術を活用して未来の電話局をつくるプロジェクト」や「子会社での事業推進」など新しい取り組みに臨んできたこと。もう1つは災害対応です。1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震などへの対応の中で、NTTのDNAである「サービスを復旧させ、つないでいく」という使命と、時代によって変わる社会の要請(避難所への臨時電話提供からWi-Fi提供など)を経験してきました。災害時に何をすべきか、被災されたお客さまにどう向き合うか、日常と異なる環境下で最適な判断が求められる立場を数多く経験し、情熱を持ちつつ冷静な判断力を備えておくことの大切さを実感しました。

今後の展望や技術者へのメッセージについて教えてください。
まずはパーパスにある「次の時代に つなぐ」という視点で、設備や社会インフラ全体をつなぎながら、「ソーシャルインフラ・イノベーション」の実現に取り組んでいくことはもちろん、NTTインフラネットという会社自体が成長しながら後輩や未来につなげていくことが大切です。
そのためにも、人材育成が重要だと考えています。人は本当に宝であり、私は社長とは「社員や社会を照らす存在」だと思います。将来の進む方向を照らし、皆が頑張れるように社員を照らし、輝かせていくことが私の役割です。現場で社員の声に耳を傾けたり、以前の会話を覚えていて声をかける、このような一見小さな行動が社員の自信や組織としての力を引き出すと信じています。トップという立場上、そういう影響力があるという自覚を持って社員や社会を照らせるよう努めていきたいです。
また、社会におけるNTTグループへの期待は非常に大きいと感じています。2030年の実現をめざして展開しているIOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想においては、その内容を体感できる大阪・関西万博のNTTパビリオンも好評です。NTTの先端技術への評価は高く、それが日本の国力や社会変革につながるという期待があるのは確かでしょう。また、インフラ事業者や自治体からの信頼感、「最後は頼りになる」と評されている自負もあります。このプレゼンスの価値は非常に大きいと思います。R&DフォーラムなどにおいてNTTの技術や取り組みに触れていただき、研究者やスタッフが積極的にコミュニケーションを図っていくことで、先端技術への評価とともにアライアンスを組んで一緒に取り組みたいという私たちの思いも伝わっていくはずです。これからもNTTグループとしての強みを活かしながら、社員とともに挑戦し続け、社会とともに未来を創っていきたいと思います。
(インタビュー:外川智恵/撮影:大野真也)
インタビューを終えて

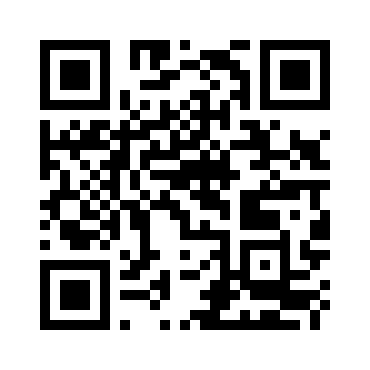




「お久しぶりですね!今日もよろしくお願いします!」明瞭で力強い声。初めてお会いした6年前と変わらない爽やかな笑顔で迎えてくださった上原社長。インタビュー中は視線を逸らすことなく、まっすぐに目を見てビジョンや信条を語ってくださいました。
前回と同様に、小麦色に日焼けをされていましたのでマラソンをお続けになられているのかと伺ったところ、「コロナ以降、レースへの参加が減り、毎朝に定期的にランニングや散歩など、緩やかに体を動かしています」とのこと。また、映画や演劇鑑賞もお続けだと言います。最近、鑑賞されたのは『国宝』。3時間という長編映画でも飽きさせない作品だったと評されました。
そんな上原社長は「社員や社会を照らす」存在として日々努力を重ねていらっしゃるようです。例えば、老若男女、幅広い年齢層と円滑なコミュニケーションを図るため、特に若手を照らし、理解するためにどんなことをしていらっしゃるかと伺いました。すると「若手世代と同じくらいの息子たちに、自分の考えはこの表現で伝わるかと尋ねたりしていますね。彼らは彼らなりに、上司と同世代の私から学び取っているかもしれませんね」と、ビジネスシーンではあまり見る機会のない一面もすんなりと教えてくださいました。上原社長のフランクさや表裏のないお話ぶりに、信頼を勝ち取り、人々を安心させるあり方を学ばせていただきました。