2025年11月号
トップインタビュー
ATM(明るく、楽しく、前向きに)マインドで自律・分散・協調型社会を支えたい
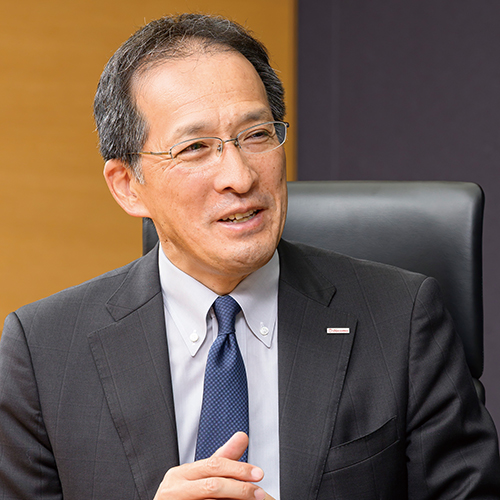
2025年7月1日にNTTコミュニケーションズは社名を「NTTドコモビジネス」に変更しました。企業と地域が持続的に成長できる自律・分散・協調型社会を支える「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざす小島克重NTTドコモビジネス代表取締役社長にドコモビジネスの重点領域やトップとしての心構えを伺いました。
NTTドコモビジネス
代表取締役社長
小島克重
PROFILE
1989年NTTに入社。2007年NTTコミュニケーションズ 法人事業本部 第一営業部 担当部長、2015年理事 第四営業本部 副本部長、2019年取締役 第四営業本部長、2020年執行役員 ビジネスソリューション本部 第四ビジネスソリューション部長、2023年常務執行役員を経て、2024年6月より現職。
「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出す
NTTコミュニケーションズからNTTドコモビジネスへと社名が新しくなりましたが、どのように受け止めていらっしゃいますか。
このたびの社名変更は単なる名称の変更ではなく、私たちのビジネスのあり方を変える大きな転機であるととらえています。
1999年、NTTが分社化された際に、長距離通信事業を引き継いだかたちでNTTコミュニケーションズが誕生しました。その後は国際事業やソリューション、データセンタ、セキュリティを次々に立ち上げるなど、現在のNTTグループの中心となっている事業にチャレンジしてきた会社です。
2020年にはNTTドコモの法人営業組織が合流して、全国に支社を再編成し、中堅・中小企業や地域に根差した事業展開が本格化しています。これまで数1000社の大企業を中心にサービスを提供してきましたが、現在では中堅・中小含め60万社を超えるお客さまにご利用いただいています。その多くがモバイルを中心としたサービスを利用されており、そこにDX(デジタルトランスフォーメーション)などの付加価値をどう提供していくかが、私たちの新たな経営課題です。
このような背景を受けて社名を「NTTドコモビジネス」へと変更しました。ドコモという名前は、地方のお客さまにも親しみやすく、ビジネスを展開するうえで響きやすいという利点があります。もちろん、社員には驚きもありました。社名変更の発表時には、戸惑いや寂しさを訴える声もありましたが、5回にわたる対話会などを通じて、私たちのチャレンジの意味や未来への展望を丁寧に説明してきました。
結果として、社員の理解と共感を得ることができました。「寂しさはあるが、新しいチャレンジに前向きに取り組みたい」など、9割近いポジティブな声が寄せられ、私自身もその言葉に支えられながら経営に臨んでいます。目下、企業と地域が持続的に成長できる自律・分散・協調型社会を支える「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざしています。
経営環境と業績、今年度の目標、来年度のビジョンについて教えていただけますか。
私たちの事業は、大きく2つの柱で構成されています。1つは、従来のNTTコミュニケーションズが担ってきた大企業向けの事業。もう1つは、NTTドコモから引き継いだ中堅・中小企業、地域向けの事業です。
大企業向けの事業では、モバイルの比率が1割程度で、ソリューションやネットワークが中心です。一方、中小企業向けの事業では、モバイルが6割近くを占めています。モバイル中心のビジネスは競争が激しく、単品売りで価格競争に陥りやすいという課題があります。実際、2022年の再編成以降、中小企業向けの事業は伸び悩み、下降傾向にありました。
この状況を打破するために、私たちはこの1年、セグメントマーケティングの強化と高速なPDCAサイクルの実践に取り組んできました。お客さまの数が非常に多い中で、業種や規模に応じたきめ細かな分析を行い、それを迅速に改善・展開する体制を整えてきたのです。
その成果は数字にも表れています。2024年度の収益は全体で約1%の成長でした。大企業層では約5%の成長を達成しましたが、中小企業層は残念ながら約3%のマイナスでした。2025年度の第1四半期では両方ともプラスに転じ、大企業が約10%、中小企業が約4%の成長を記録しています。
ICT業界平均が毎年約6%の成長であることを考えると、私たちの取り組みが着実に成果につながっていると実感しています。2025年度の目標は、法人事業で「2兆円の売上」を達成することです。これは当時のNTTドコモ、NTTコミュニケーションズ、NTTコムウェアが統合された際に掲げた中期目標のゴールでもあります。現在、全社一丸となってこの目標に向かって邁進しています。
来年度も6%以上の成長率を維持していくことが定量的な目標です。これを達成するために、まず大企業向けでは、お客さまのビジネスをどう一緒に創っていくのか、それを実現するために、私たちはどのようなプラットフォームを提供していくのか。そういった観点で、営業の質をさらに高めていくことに重点をおきます。
一方、中堅・中小企業向けには、モバイルのビジネス向けプランを新たに導入します。これはNTTドコモ時代にはなかった法人専用のサービスとなります。これにより、モバイルの基盤を固め、そこにAI(人工知能)やDXなどの付加価値を加えていきます。
例えば、AIを活用した「Stella AI for Biz」は中小企業向けに開発したもので、業務効率化や経営支援に役立つツールです。また、「BUSINESS LOAN」の提供も開始し、金融面からも企業の成長を支援します。
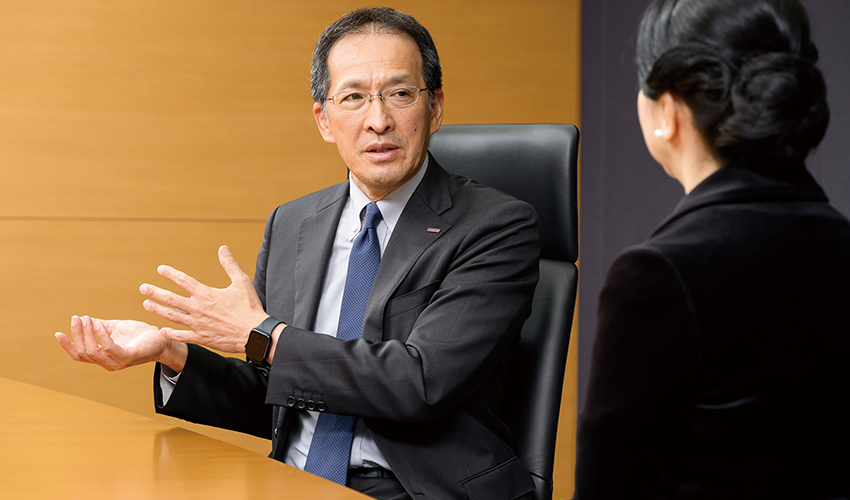
AI、IoT、DX、IOWNで未来を築く
NTTドコモビジネスではどのような領域に力を入れていくのでしょうか。
私たちは4つの分野、デジタルBPO(Business Process Outsourcing)、AI、IoT(Internet of Things)、中小企業DXを重点領域に取り組んでいます。
まずデジタルBPOですが、2024年のトランスコスモス社との戦略的連携により、さらなるマーケットの開拓に取り組んでいます。現在4つのソリューションモデルを提唱し、成果も出てきている分野です。お客さまの非コア業務の効率化を実現するソリューションを提供するとともに、AIやデータを使い、サービスの付加価値を一層高めていきます。
次にAIですが、私たちは単にAIを「提供する」だけでなく、AI時代にふさわしいICTプラットフォームを構築することをめざしています。そこで、私たちは「AI-Centric ICTプラットフォーム」という構想を打ち出しました。これにより、お客さまがAIの利用状況に応じて、ネットワーク帯域をポータル上で分単位にコントロールできたり、自動運転などには、MEC(Multi-access Edge Computing)により近隣のエッジデータセンタで高速処理を実施したり、小口のAI使用では、コンテナデータセンタを導入したりと、柔軟で効率的なAI利用環境をさまざま提供していきたいと考えています。
IoTはNTTドコモとNTTコミュニケーションズが統合したことで、もっとも象徴的に進化した領域だと感じています。数年以内にマーケットリーダのポジションに並ぶことを目標に、業界別にIoTプロジェクトを立ち上げました。スマートメータや自動車関連の領域では成果が出ており、今後は新しい売り方についてもチャレンジしていきます。
中小企業DXについては、さきほど話したとおり、モバイルを起点に、AIやIoT、DXなどの付加価値を組み合わせることで、企業の業務効率化や経営改善を支援していきます。
そして、次世代のインフラとして夢のあるIOWN(Innovative Optical and Wireless Network)についてですが、NTTグループとしては先頭を切って国内外へ実装していきたいと考えています。データセンタ間の接続ニーズはすでに高まっていますが、将来はAIなどの学習・分析にもIOWNを活用していきたいと考えています。また、地域の振興や産業を支えるインフラとしてIOWNを導入しようとする動きがあります。北海道ではラピダス社の創業を機に、周辺へ半導体関連会社が集結する流れもあり、「HOKKAIDO IOWN CAMPUS」という事業コンセプトを掲げ、地域と連携した未来型インフラの実装に臨んでいます。
入社からこれまでの歩みをお聞かせください。今のお考えに至る転機となったことはありますか。
私が入社したのは1989年で、最初に配属されたのは、固定電話機販売の営業支援部門でした。1年間は電話機営業を担当し、その後、システム開発部門に異動して開発業務に携わりました。開発職は希望していなかったのですが、適性検査の結果で配属されたようです。その後、企画や人事の仕事を経験してから営業職に戻り、自動車会社の担当営業として、現場でお客さまと向き合いました。正直なところ、営業の仕事は苦手意識を持っていました。例えば、トラブルが発生した際に代表して叱られることがあり、悩むこともあったのです。
そんな私に転機が訪れたのは、ある自動車会社のトラブル対応をしていたときのことです。徹夜で対応し、疲れ果てていた朝、お客さまの役員が私にこう言ってくださったのです。「小島くん、ありがとう。逃げないで頑張ってくれたね」。その言葉にビビビっときました。そこから私はお客さまの声に耳を傾け、ニーズをかたちにすることの大切さを強く意識するようになりました。
ところで、トップとしての視点に立つと、物事の見え方は大きく変わりました。会社全体、日本経済の中での自社の位置付け、社会への貢献など、今まで以上に多角的な視点で考えるようになりました。振り返ってみると、さまざまな業界を担当し、各業界の特性を理解し、人脈を築いてきたことは、今の経営に大きく役立っています。「全体を俯瞰できる視点」を持つことができたのは、非常に幸運でした。
ただ、決断には迷いが伴うこともあります。情報が100%そろうことはありません。だからこそ、判断の軸を持つことが重要です。私が大切にしているのは、「それが会社の成長につながるか」「インテグリティ(誠実さ)を保てるか」、そして「社員の目を見て、やる気を感じられるか」です。社員の目には、真剣さや情熱が宿っています。最後の頑張りは、現場の社員の気持ちにかかっていると信じ、コミュニケーションを大切にしています。支社や職場を巡回したり、社員に直接珈琲を手渡しする「コジー珈琲」を実施したりして距離を縮める努力を続けています。

夢のある事業ポートフォリオをつくり、お客さまに驚きと感動を届け、ワクワクする職場をつくる
トップの使命とはどのようなことだとお考えですか。
「夢を示すこと」「会社の未来に希望を持たせること」だと考えています。社員は「自分のやりたいことを実現するために働く」時代ですから、会社そのものが魅力的でなければなりません。社員が「この会社で働きたい」「この会社で成長したい」と思えるような未来を描くことが、トップの責任だと考えています。
私は社長就任時に、最初の経営会議で3つのメッセージを伝えました。まず「夢のある事業ポートフォリオをつくる」こと。私たちの事業がこれからも成長し続けるという希望を示し、社員が未来にワクワクできるような、そんな事業を創りたいと思っています。次に「お客さまに驚きと感動を届ける」こと。言い換えれば、期待を超えるサービスを提供するという意味です。ニーズを先取りした提案や心に響く対応をめざしています。最後に「社員にとってワクワクする職場をつくる」こと。職場が楽しく、前向きで、笑顔があふれる場所であることが、社員の力を最大限に引き出す原動力になると信じているからです。私はよく「ATMマインド」という言葉を使います。ATMとは「明るく、楽しく、前向きに」のアルファベットの頭文字です。これは私自身が日々意識していることで、どんなに困難な状況でも心の内で「大丈夫」と言い聞かせ、笑顔を忘れず、前向きに取り組んでいます。

最後に皆さんへのメッセージをお願いいたします。
私たちNTTドコモビジネスは、これからの社会において、産業・地域DXのプラットフォーマーとして進化していきたいと考えています。AI、IoT、IOWNなどを活用しながら、企業の成長を支え、地域社会の活性化に貢献する。そんな未来を、社員、パートナー、そしてお客さまとともに築いていきたいのです。
また、NTTグループには、時代の先駆けとなる研究に取り組んでいる研究者、技術者が多数在籍しています。それを社会にどう届けるかが私たちの役割です。研究成果をサービスに変え、社会で使われるかたちにする。そのプロセスを、私たちとともに考えていただけたらうれしく思います。
そして、社員の皆さん。日々、それぞれの持ち場で全力を尽くしてくださっていることに、心から感謝しています。昨年度はさまざまな課題もありましたが、皆さんの努力のおかげで、数字も回復してきました。お客さまの事業を支え、お客さまへ驚きと感動を届けるために、今後も明るく、楽しく、前向きにのATMマインドで一緒に頑張っていきましょう!
そして、パートナーの皆様。社会課題の解決のためには皆様との連携が不可欠です。6月には新たなパートナープログラムを開始し、より多くの企業と協業できる体制を整えました。「OPEN HUB Park」では、共創の場としてのスペースも用意しています。ぜひ、新しい価値を共に生み出していきましょう。
(インタビュー:外川智恵/撮影:大野真也)
インタビューを終えて

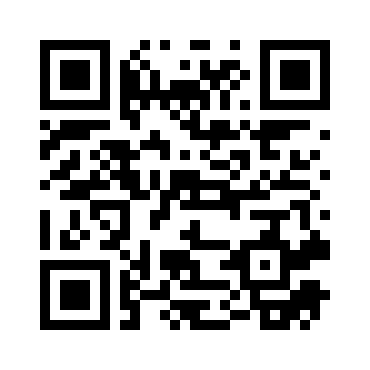




分刻みのスケジュールで次々と大きな仕事を捌くトップへの取材は、限られた時間の中で存分にトップの魅力を引き出せるよう、試行錯誤する機会となります。小島社長も「超」が付くほど多忙なNTTグループのトップのお一人です。前後の予定も詰まりに詰まっているはずなのに、しわ1つないスーツ姿で静かな威厳を漂わせ、インタビュー会場に現れました。
インタビューを文字に起こすとおおむね1万5000から2万文字になるのですが、小島社長のお話には、各項目のタイトルとなるような印象に残る言葉が散りばめられていました。
そんな小島社長のご趣味の1つはスポーツ観戦。野球やラグビー、サッカーを楽しんでいらっしゃるそうです。また、浅田次郎が好きだとか。「作品によって作風が違うのが面白く、あらゆる感情を引き出してくれます。疑似体験をしたくて読んでいるように思いますね」と小島社長。チームスポーツの観戦で真剣みやチームワークを、そして、浅田作品で多角的な視野を養うことは、「最後は社員の目を見て決める」という小島社長の逃げずに真正面から向き合う姿勢につながっているのかもしれないと感じたひと時でした。