2025年8月号
特集2
「NTT コミュニケーション科学基礎研究所 オープンハウス2025」開催報告
- 情報科学
- 人間科学
- AI
NTTコミュニケーション科学基礎研究所では、最新の研究成果を多くの方々に知っていただくイベントとして、2025年5月20〜22日の3日間、大阪・京橋にあるNTT西日本i-CAMPUS内のQUINTBRIDGEとPRISMを会場に「オープンハウス2025」を開催しました。来場者は完全現地参加型の事前予約制とし、1078名(昨年比2割増)の方々にご来場いただきました。本稿ではその開催模様を報告します。
熊野 史朗(くまの しろう)/渡邊 直美(わたなべ なおみ)
田中 佑典(たなか ゆうすけ)/上村 卓也(こうむら たくや)
渋江 遼平(しぶえ りょうへい)/林 定雄(はやし さだお)
藤永 裕之(ふじなが ひろゆき)/青山 一生(あおやま かずお)
宮内 美樹(みやうち みき)
NTTコミュニケーション科学基礎研究所
オープンハウスの概要
NTTコミュニケーション科学基礎研究所(CS研)は創立以来、人と人、あるいは人とコンピュータの間の「こころまで伝わる」コミュニケーションの実現をめざし、時代を先取りした基礎研究に取り組んでいます。その最新成果を「見て、触れて、感じていただく」イベントとして、例年5月末から6月上旬にNTT京阪奈ビル(京都府精華町)にて「NTTコミュニケーション科学基礎研究所 オープンハウス」を開催してきました。2020年から2022年の3年間は、新型コロナウイルス感染症対策として現地開催を取りやめ、特設ウェブサイト上で講演・展示動画を公開するオンライン開催としました。2023年には、関西主要駅からのアクセスが良いNTT西日本のオープンイノベーション施設「QUINTBRIDGE」(大阪市)を会場に、4年ぶりに現地での展示開催を再開しました。翌2024年には、隣接する「PRISM」も利用し、2019年以来となる現地での招待講演や研究講演を含むフル現地開催を実現しました。そして2025年は、昨年に引き続き「QUINTBRIDGE/PRISM」を会場として5月20〜22日の3日間、フル現地開催を行いました。本年は「知の交響で奏でる わたしたちの未来」をテーマに、招待講演1件を含む講演6件(計11回)を「QUINTBRIDGE」で、研究展示20件を「PRISM」で実施しました。昨年同様にスロット制の事前予約方式を採用し、来場者は昨年比約2割増の延べ1078名となりました。講演では、研究講演(5件)を各2回実施するという新たな試みを行い、新設した自由席も奏功して、延べ1037名(1講演平均94名)の方々に聴講していただきました。
招待講演
招待講演では、慶應義塾大学 名誉教授・一般社団法人 今井むつみ教育研究所 代表の今井むつみ先生に「人はどのように知識を構築していくのか—記号接地とアブダクション」と題する講演をいただきました(写真1)。「生成AI(人工知能)がスマートフォンやクラウドサービスを介して生活インフラの一部となりつつある現在、AIは私たちの知性にどのような影響を与えるのか」この根源的な問いに対し、今井先生は「AIと人間の思考・学習の違い」を鍵に据え、言語習得研究の知見を踏まえた議論を展開されました。
講演の第1のキーワードは「記号接地問題」です。1990年代にカナダの認知科学者S. Harnadが提起したこの問題は、身体を持たないAIが外界の対象を言語記号に結びつけられず、真の意味理解に至らないという課題を指摘します。「人間の子どもは「ミルク」「パン」などの語を五感全体で経験しながら対象に接地させますが、AIは別の記号の連鎖としてしか定義できず、言語の海を漂流し続ける」この対比が示されました。
第2のキーワードは「アブダクション推論(仮説形成推論)」です。子どもは獲得した語を語彙全体の中に位置付け、範囲を推論しながら意味体系を構築します。この過程は科学者が実験と修正を繰り返しながら仮説を洗練する営みと同型であり、人間の知識創造の源泉であると説明されました。対照的に、多数のデータから帰納統計的にパターンを抽出する現在のニューラルネット型AIは、因果メカニズムを仮定するアブダクションを欠き、新たな知識の発見や概念の枠組み転換が難しいと指摘されました。
さらに今井先生は、アブダクション推論に不可避の「誤り」とその修正プロセスこそが、人間の柔軟で創造的な学習を支えると述べられました。AIが汎用的で自律的な学習を実現するには、記号接地問題の解決と、どの知識をいつ活用するかを判断する「フレーム問題」の克服が重要であり、これらは人間理解とAI開発双方の核心課題になるとまとめられました。
本講演は、生成AI時代における言語・認知研究とAI技術の接点を提示し、多様な参加者から活発な質疑が寄せられました。講演映像は後述の研究講演と同様に当オープンハウスの特設ウェブサイト(1)で約1年間公開予定です。

研究講演
研究講演では、CS研の最新成果の中から注目度の高い5テーマを選びました。各講演後には活発な質疑が行われ、高い満足度(全講演平均90%以上)が来場者アンケートでも裏付けられました。
① 「身体に根ざした共感の科学から、つながる家族のウェルビーイングへ〜身体を介した共感メカニズムの解明および身体性情報伝送技術を活用した離れた家族のつながり支援〜」と題した村田藍子(人間情報研究部)による講演では、表情や心拍などが無意識のうちに相手と同調することで生まれる情動的共感に注目し、遠隔家族間での情動の共有を実現する触覚伝送デバイスを紹介しました(写真2)。離れて暮らす家族のQOL(Quality of Life)向上に向けた応用が期待されます。

② 「気の利く対話AIのための『空気を読む』技術〜マルチモーダル情報を用いた対話の場・関係の理解とインクリメンタル応答生成〜」と題した千葉祐弥(協創情報研究部)による講演では、対話場面の雰囲気や相互関係を、言語・声色・表情といったマルチモーダル情報から推定し、会話の流れに合わせて適切なタイミングで気の利いた応答を生成する新しい対話エージェントの試みを紹介しました(写真3)。日常生活の中でさまざまな情報から場面を理解し、人を身近にサポートする対話システムの実現が期待されます。

③ 「音の聴き方を自ら学ぶAI〜自己教師あり学習によるさまざまな音の汎用表現学習技術から、大規模言語モデルを活用した音の理解の最前線へ〜」と題した仁泉大輔(メディア情報研究部)による講演では、大量の環境音を自己教師ありで学習して多様なタスクへ転用可能な汎用音響表現を獲得し、さらに大規模言語モデルと連携させることで「音の意味理解」へと拡張する最新の研究を紹介しました(写真4)。日常生活音による健康状態のモニタリングなど、幅広いサービスへの応用が期待されます。

④ 「データの交わりに隠れた未知の知識を発見する〜無限の仮説を考慮して生体現象を解釈するAIモデルと高信頼メディカルヘルスケアへの展望〜」と題した中野允裕(メディア情報研究部)による講演では、無限個の仮説を扱えるノンパラメトリックベイズ法に基づき、生体現象データを統合解析して未知の因果構造を抽出する方法を紹介しました(写真5)。関係データ解析・系統解析・軌跡推論の3つの応用事例を示し、高信頼なメディカルヘルスケア実現へ道を拓く手法を提示しました。

⑤ 「ロボットに心を感じる子どもたち〜未来の幼児教育を支える学習コンパニオンロボット〜」と題した奥村優子(協創情報研究部)では、幼児が社会的ロボットとかかわる実験を通じて、ロボットの視線や呼びかけが子どもの利他的行動や記憶を促進することを示しました(写真6)。ロボットが人の生活に浸透するこれからの時代において、学習コンパニオンロボットがどのように受け入れられ、幼児教育にどのような影響をもたらすかという新たな視点を提案しました。

研究展示
今年のオープンハウスでは「データと学習の科学」「メディアの科学」「コミュニケーションと計算の科学」「人間の科学」の4カテゴリに関する最新成果20件を展示しました。各展示は現地会場において研究員によるパネルやディスプレイを用いたインタラクティブな説明を実施し、その中でも12件に関してはより直感的に研究を理解していただくためのデモを実施しました(写真7)。以下は、各カテゴリの展示名です。

■データと学習の科学(6件)
・多重の思考を相互に協調させながら学習するAI
〜決定木の重ね合わせ学習に基づく透明性の高いデータ解析〜
・少ないデータで高精度な空間予測を実現します
〜ニューラルガウス過程に基づくメタ学習技術〜
・ラベルなしデータだけで新環境に適応するAI
〜ソースフリードメイン適応の理論的解釈〜
・超低消費電力を達成する光AIの実現に向けて
〜特殊な構造を考慮した光ニューラルネットワークの訓練法〜
・光と物質の相互作用を結ぶ数理
〜非可換調和振動子の数理が示す新たな統一性〜
・ノイズがあっても高精度な量子計算を実現!
〜人工ノイズでノイズを整えて量子計算の精度を高める技術〜
■メディアの科学(4件)
・空中に触感を生み出す
〜集束超音波を用いた非接触な触感の再現〜
・騒がしい環境で録音音声をクリーンな音声に変換
〜多ストリーム拡散モデルのアンサンブル推論による音声強調〜
・リアルタイム音声変換を用いたライブ配信
〜高音質で低遅延なリアルタイム音声変換〜
・データ圧縮の効率を高めます
〜複数の符号木による汎用的で高効率な可逆圧縮符号化〜
■コミュニケーションと計算の科学(4件)
・社会的ロボットが見ていると良い子にふるまう
〜ロボットとのやり取りが幼児の思いやり行動を促進する〜
・第二子の言語発達の緩やかさは小学生で解消する
〜年上きょうだいの有無が子どもの言語発達に及ぼす影響〜
・過不足のない忠実な機械翻訳を実現します
〜単語対応を用いた大規模言語モデル機械翻訳の選好最適化〜
・自分を取り巻く人間関係の変化をSNSでとらえる
〜Social Orbit—SNSログを用いた関係変化の可視化法〜
■人間の科学(6件)
・手を引くAIが街をご案内
〜牽引力覚デバイス「ぶるなび4」の社会実装に向けたコラボ実現〜
・入院中の赤ちゃんと家族のつながりを支援します
〜NICUの新生児と家族をつなぐ身体性オンライン面会〜
・目でとらえる打撃の真髄
〜プロ野球選手の視線データが明かす一流打者の視線移動戦略〜
・身体運動に宿る“選球眼”
〜身体を制御する能力が迅速な意思決定能力を支える〜
・集中力を高める特殊な光
〜ipRGCを変化させるステルス光を用いた心理状態の改善〜
・休日の寝坊、やはり問題あり!?
〜睡眠パターンに現れる睡眠負債が反応速度に与える影響〜
オープンハウスを終えて
2025年のオープンハウスでは、昨年に引き続き事前予約制を導入し、安全性と快適性に配慮しながらも、会場配置の刷新、講演回数の増加、自由席の導入など踏襲と挑戦のバランスを図ることで、より多くの方々にご来場いただけました。CS研の研究員にとっても、多彩な経歴を持つ来場者の皆様と直接会話し、自由闊達なディスカッションを行えたことは大変有意義でした。また、QUINTBRIDGEのメインステージでは、会場全体を活用したレイアウトにより、聴講の方々が講演者を間近に感じつつ質疑応答を交わすことができました。PRISM会場でも、20件の展示をコンパクトにまとめたことで、効率的にご覧いただけたと感じています。本イベントの開催にご協力くださった皆様に、心より御礼申し上げます。
■参考文献
(1) https://www.kecl.ntt.co.jp/openhouse/2025/index.html

(左から)林 定雄/宮内 美樹/田中 佑典/上村 卓也/熊野 史朗/渡邊 直美/渋江 遼平/藤永 裕之/青山 一生
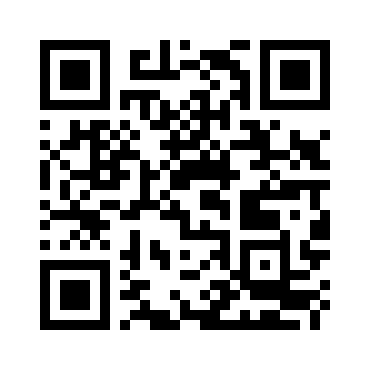




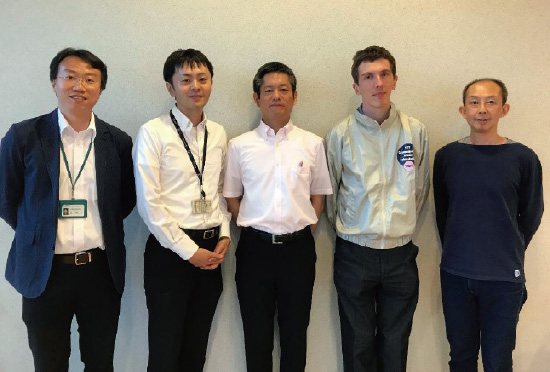




今後ともCS研の研究にご注目ください。