2025年8月号
特集1
コミュニケーションのあり方を問いかける「ふれあう伝話」と「せかいがきこえる伝話」――電話から、伝話へ
- 2025年日本国際博覧会
- 未来のコミュニケーション
- IOWN
NTTパビリオン屋外中間領域に、触覚で人の存在を伝え合う「ふれあう伝話」と、物語を聴く「せかいがきこえる伝話」を展示しています。「ふれあう伝話」はIOWN(Innovative Optical and Wireless Network)による低遅延通信で振動も共有し、新しい触れ合いを体験可能にします。「せかいがきこえる伝話」ではレトロな電話機を使い、多様なつながりの物語を聴くことができます。これらはこれまでの、そしてこれからのコミュニケーションを伝え合うメディアとしての体験展示です。
駒﨑 掲(こまざき かかぐ)†1~3/渋沢 潮(しぶさわ うしお)†1,2
渡邊 淳司(わたなべ じゅんじ)†1~3/望月 崇由(もちづき たかよし)†1
NTT人間情報研究所†1
NTT社会情報研究所†2
NTTコミュニケーション科学基礎研究所†3
公衆電話から125年、“伝話”がつなぐ未来のつながり
2025年4月13日、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)が開幕しました。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げる本万博では、社会や人々のあり方に変革をもたらす新しい技術や価値観が提示されています。その中でNTTは、2種類のつながるメディアを展示しています。音声や映像だけでなく、“触覚”を通じて人と人をつなぐ遠隔触覚コミュニケーションメディア「ふれあう伝話」、レトロな電話機を用い“つながりの物語”を、受話器を通して聴くことができる「せかいがきこえる伝話」を出展しています。今年は日本で最初の公衆電話が登場してからちょうど125年という節目にあたります。1900年、東京に設置された初の公衆電話は、以降、公共の場におけるコミュニケーションのインフラとして、多くの人々の想いをつないできました。「ふれあう伝話」は、そうした歴史を受け継ぎながら、公共の場で生まれる偶然の出会いや、初めて会う人とでも触れ合うコミュニケーションが気軽にできてしまう、そんな新しいコミュニケーションのあり方をめざしています。また「せかいがきこえる伝話」は人と人が出会い、響き合う物語に耳を澄ませることを通じてつむいできたコミュニケーションのかたちを追体験することができ、通信を通して生まれる人と人のつながりの豊かさを、物語を聞くことで追体験する機会を提供しています。
「ふれあう伝話」がつなぐ未来
「ふれあう伝話」は、「未来の電話をつくる」というテーマから始まりました。1970年の大阪万博のころにおける「未来の電話」とは、固定電話をワイヤレス化し携帯性が加わるといった、主に機能面の進化をさしていました。しかし、現代における通信技術の成熟につれて、求められるのは機能や情報量の多さでなく、「豊かで実感を伴うつながり」を実現するかという質的な変化となりました。
そうした背景から、「電話から、伝話へ。」というコンセプトに至りました。私たちは、これまでの“電話”が担ってきた「情報を伝える道具」としての役割を超えて、相手の存在そのものを伝える「伝話」へと進化させることをめざしています。単に言葉をやり取りするだけではなく、手のひらに伝わる振動や心拍を感じることで、「今、つながっている」という感覚を直感的に届けることができます。触れ合いの感覚を通信に取り入れていくことは、単に情報を交換することではなく、信頼や共感、そして“実感”を伴ったつながりを育むことです。「ふれあう伝話」は、そんな未来のコミュニケーションの原型であり、人と人、心と心をつなぐための新たな道をつないでいきます。
振動伝送技術
NTTの研究所では、誰もが共通して持つ感覚である「触覚」に着目し、従来の映像や音声によるコミュニケーションに加えて、触覚を感じられる情報通信技術の研究を進めてきました(1)。こうした身体的なコミュニケーションを通じて、人と人との“つながり”をより深く、直感的に実感できる新たな体験をめざしています。
触覚には温度、圧力、振動などさまざまな種類があり、その中でも、「ふれあう伝話」では特に「振動」を扱っています。振動情報は、音声データと同様に時系列の波形データとして扱えるという特性を活かして伝送しています。送信された振動の波形データが装置に届くと、内蔵された振動子がその波形に合わせて動作し、受信者の手のひらにリアルな触感として伝わります。
「ふれあう伝話」は、映像・音声・振動の3つの情報を双方向でやり取りができる遠隔触覚コミュニケーションメディアです。ユーザが机や、丸い手のマークがついたパネルに触れると、その動作がリアルタイムに計測され、振動触覚として音声波形に変換されて、IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)を経由して相手側に送信されます。受信側では同様に振動子が作動し、振動として再現されることで、あたかも相手と触れ合っているかのような感覚が得られます。
このように、「ふれあう伝話」は、離れていても身体感覚を共有できる新しいコミュニケーションのかたちを実現しています。
IOWNで触覚伝送技術がつなぐ「ふれあう伝話」
また、「ふれあう伝話」のリアルタイムな触覚体験を可能にしているのが、NTTが開発した次世代通信基盤IOWNです。IOWNは、最先端の光技術を使って、豊かな社会を創るための構想です。IOWNは従来のネットワークと比較して、非常に低い遅延と高い転送性能を備えています。そのため、例えばハイタッチのように同時に触れ合いを生むインタラクションでも、ずれを感じることなく、まるで本当に目の前の人と触れ合っているかのようにハイタッチの感覚を実現します。触れたその瞬間、相手の存在に実感を持つことができます。従来の触覚通信では、ネットワーク遅延がリアルタイム性の障壁となっていました。これを克服するIOWNの導入により、まさに「今、そこにいる」ような存在感を通信越しに再現できるようになりました。
実際に、「あっち向いてホイ」やじゃんけん、そしてハイタッチの体験を通し、来場者の方からずれのないコミュニケーションに驚きの声をいただいています。
2つのコンセプトでつなぐ「ふれあう伝話」
今回の大阪・関西万博では、「ふれあう伝話」は2つのコンセプトで展示されています。それぞれが異なる場所にある意義やその場に合うように設計されており、訪れる人々に多様な触れ合いの体験を提供します。
〈「ハイタッチでつなぐ」ふれあう伝話〉(図1)は、日本館と関西国際空港にそれぞれ1台ずつ設置されています。関西国際空港に到着した海外からの来訪者と、万博会場の日本館にいる来場者が、「ふれあう伝話」を通してあいさつしながらハイタッチを行い、その振動を互いに共有することができます。
モニタの両脇には丸い手のマークが設けられており、そこに触れることで相手にも振動が伝わります。また触ったときに相手側の手のマークが光ります。言語の壁を越え、ハイタッチした感覚を伝え合うことができます。
初めて会う相手であっても、手のひらに伝わる振動は、互いの存在を自然と実感させてくれます。この触覚的なやり取りによって、日本館の来場者は“向こう側”にいる人々への関心を抱き、訪問者もウェルカムな気持ちを受け取り、万博への期待を高める効果が期待されます。また触覚によるコミュニケーションは、非言語でも楽しめることから、言語の壁を越えてさまざまな人をつなぐことができます。
〈「いのち」ふれあう伝話〉(図2)は、NTTパビリオンと、同じ万博会場内にある生物学者の福岡伸一氏がプロデュースするシグネチャーパビリオン「いのち動的平衡館」を結んでおり、触れる感覚に加えて、心臓の鼓動まで共有することが可能です。
それぞれのモニタの前には机が設置されており、来場者が手を置くと、その触れた感覚が相手の机に振動として伝わります。振動を送った際には、相手側の机の手のマークが光り、視覚的にも相手側に情報が伝わっていることが確認できます。
また、NTTパビリオン側には聴診器型のマイクが設置されており、胸に当てると心拍を計測し、相手側のテーブルに“鼓動”として届きます。送っている人の鼓動は、自分のテーブルでも振動として感じられます。手のひらに伝わる鼓動は、他者の“いのち”を感じ、個々の存在が他者と関係性の中で生きていることを、身体を通して理解する場を提供しています。


過去の研究がつなぐ、触覚コミュニケーションの系譜
「ふれあう伝話」の背景には、NTTが長年取り組んできた身体性メディア研究の蓄積があります。2019年からNTTインターコミュニケーション・センター(ICC)で展示されていた「公衆触覚伝話」(2)は、映像と音声に触覚情報を加えることで、対面での触れ合いを再現する試みでした。湾曲したモニタとテーブルが一体化したこのメディアは、遠隔にいながら一緒にそこに“いる”感覚を提供し、初対面の人どうしでも積極的に触れ合える場をつくり出しました。また、〈「いのち」ふれあう伝話〉で使用された聴診器型デバイスは、「心臓ピクニック」(3)(4)というワークショップで活用されていた「心臓ボックス」の技術に基づいています。このボックスは、胸に当てた聴診器から取得した心拍を振動に変換し、他者に手渡すことで命の存在感を伝えるものでした。さらに〈「ハイタッチでつなぐ」ふれあう伝話〉には、2020年から研究を進めている「リモートハイタッチ」(5)の技術が応用されています。新型コロナウイルス感染症の拡大により無観客で行われたスポーツ大会などで、選手と家族がハイタッチで応援の気持ちを共有するために活用されました。映像・音声に加えて振動の情報を遠隔で送り合い、触感を伴う遠隔ハイタッチ体験を実現するものです。「リモートハイタッチ」は、何らかの理由によって離れた場所にいる人どうしでも、喜びや応援の体験を身体感覚が伴うかたちで共有することで、単純に映像・音声でつながるよりも深い心と心の“つながり”が醸成されることをめざしています。この「リモートハイタッチ」の取り組みは、これまで、病院に長期入院中の小児が、小児の憧れのバスケットボール選手たちを応援するイベントや、新型コロナウイルス感染症蔓延下、無観客で行われたフェンシング選手権において、アスリートと遠隔の家族とをつなぐ状況下で実施されてきました。
「せかいがきこえる伝話」がひらく、つながりの記憶
〈「いのち」ふれあう伝話〉の隣にある、もう1つの展示「せかいがきこえる伝話」は、音声を通じて人と人の物語を届けるメディアです(図3)。レトロなスタイルの電話機が3台(黄色と赤色のプッシュ式公衆電話と水色のプッシュ式家庭用電話機)が並んでおり、それらの受話器を取り、3桁の番号を押すと、そこから“つながりの物語”をテーマにしたさまざまなストーリーが流れてきます。
例えば、「#408 グッドナイト」では恋人どうしの寝る前の会話、「#373 裏側」では地球の裏側に住む少年との国際電話、「#396 春」では受験に合格したことを母に報告する声が流れます。10種類の物語(英語版も同様に10種類)は、家族、社会、地球、生命など、さまざまなスケールのつながりを扱い、聴く人の心に語りかけます。人と人のつながりの価値に改めて思いを馳せるきっかけとなる体験です。
この展示は、単なる音声コンテンツの再生装置ではなく、「聴く」という行為そのものに価値を見出す体験装置です。重みのある受話器を手に取ることで、聞き手は自然と物語へと気持ちが導かれていきますし、プッシュボタンで番号を選ぶ操作は、10種類のストーリーのタイトルから自らが選び、能動的な物語との出会いにつながります。そして体験者は、それぞれの物語を自身の記憶や感情と重ね合わせながら受け取り、過去の出来事や身近な人との記憶を呼び起こすきっかけにもなります。
こうして「せかいがきこえる伝話」は、来場者1人ひとりの体験を通じて、人と人とのつながりの深さや多様性、そしてそれを支えてきた“電話”というメディアの歴史的意義を思い起こすことにつながります。
NTTが長年培ってきた通信技術は、単に高速・大容量のデータ伝送を可能にするものだけではなく、人と人とのつながりによって生まれる物語を支え続けてきました。「せかいがきこえる伝話」は、そうした日常のかけがえのない瞬間を再構築し、社会や世界、そして私たち自身の心のあり方に新たな気付きをもたらす展示となっています。

Well-beingの視点からみたつながりの物語
現代の企業には、単なる利益追求にとどまらず、製品やサービスを通じて社会や環境に貢献する姿勢が求められています。NTTはこれまで、電話や通信技術を通して人と人をつなぐ取り組みを続けてきました。こうした“つながり”は、Well-being*にとって、欠かせない要因です。「せかいがきこえる伝話」は、かつて電話が育んできた多様な“つながりの物語”を、レトロな電話機を通じてもう一度体験できる展示です。それぞれの物語には、人とのつながりの温かさや気付き、すなわちさまざまな人々のWell-beingを読み取ることができます。ぜひ、会場にて受話器を手に取り、Well-beingなストーリーに耳を傾けてみてください。
* Well-being:身体・精神・人とのつながりなど、さまざまな側面を含む、それぞれの人のよく生きるあり方、よい状態を意味します。本展示では、さまざまな人のWell-beingに関する物語を音声によって提示しています。
情報通信からつながりの本質へ
「ふれあう伝話」も「せかいがきこえる伝話」も、人と人がつながることの意味を問い直しています。テクノロジは人と人の距離を縮め、情報のやり取りを高速化しました。そこへさらに振動を通じて触れ合うことで、相手の存在を感じることができる「ふれあう伝話」、人とのつながりの物語に耳を傾けることで、自身の物語を呼び起こす「せかいがきこえる伝話」。こうした体験は、コミュニケーションの本質に立ち返りながらも、未来の可能性を拓くものです。
おわりに
万博会場にある2つの「伝話」は、それぞれ、コミュニケーションのあり方を問いかけています。「ふれあう伝話」は、技術革新だけでなく、人と人とのつながり方そのものに問いを投げかけるメディアです。音声や映像による情報のやり取りを越え、触覚という“身体的な実感”を共有することで、コミュニケーションはより深く、豊かなものになる可能性を秘めています。「せかいがきこえる伝話」は、人と人の関係そのものをかたちづくる物語を通じて、その意味を問い直しています。
125年前に公衆電話が公共空間に登場したように、「伝話」もまた、これからの社会における新たなインフラとなるかもしれません。2025年の万博という機会を通じて、多くの方々が未来の「伝話」に触れ、感じ、つながり合うきっかけとなることを期待しています。
■参考文献
(1) 駒﨑・渡邊:“遠隔地をつなぐ振動伝送体験デザイン原理の構築に向けて”電子情報通信学会通信ソサイエティマガジン, Vol. 17, No. 1 p. 32-41, 2023.
(2) 早川・大脇・石川・南澤・田中・駒﨑・鎌本・渡邊:“高実在感を伴う遠隔コミュニケーションのための双方向型視聴触覚メディア「公衆触覚伝話」の提案,”,日本バーチャルリアリティ学会論文誌,Vol. 25,No. 4, pp. 412-421, 2020.
(3) 渡邊・川口・坂倉・安藤:“心臓ピクニック”:鼓動に触れるワークショップ,”日本バーチャルリアリティ学会論文誌,Vol. 16,No. 3,pp. 303-306, 2011.
(4) 坂倉・渡邊・川口・安藤:“「生命」のシンボル・グラウンディング 鼓動に触れるワークショップ「心臓ピクニック」の評価と展開,”アートミーツケア学会オンラインジャーナル,Vol. 4,pp. 20-29, 2012.
(5) 駒﨑・渡邊:“触覚伝送による"リモートハイタッチ":アスリートの家族間コミュニケーションや聴覚障がい者との観戦検討, ”,日本バーチャルリアリティ学会論文誌,Vol. 27,No. 1,pp. 2-5, 2022.
(6) https://www.rd.ntt/iown/
(7) https://socialwellbeing.ilab.ntt.co.jp/tool_connect_vibrotactilephone.html
(8) https://www.ntt-west.co.jp/brand/

(左から)駒﨑 掲/渋沢 潮/渡邊 淳司/望月 崇由
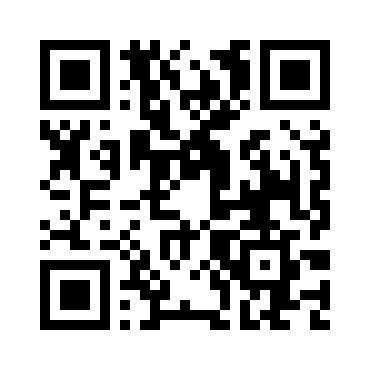







「ふれあう伝話」は、未来のつながり方を体感できるメディアです。初めて会う人と触れた瞬間、遠くの相手の存在を実感することができます。ぜひ万博会場で、初めて会う方との “触れ合い”を体感してみてください。