2025年8月号
特集1
はじめに――幸せな進化をつくる未来のコミュニケーション
- 2025年日本国際博覧会
- 未来のコミュニケーション
- IOWN
本特集では、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)におけるNTT研究所の取り組みについて、NTTパビリオン関連を中心に最新の技術およびその活用方法を紹介します。特集冒頭の本記事では、NTTが万博で伝えたい思いの1つである「まるで隣にいるような、存在を感じる未来のコミュニケーション」の概要について解説します。
日高 浩太(ひだか こうた)/島村 潤(しまむら じゅん)
望月 崇由(もちづき たかよし)/平尾 美佐(ひらお みさ)
NTT人間情報研究所
背景 ~コミュニケーションの変遷と課題~
今私たちは、スマートフォンひとつで世界中の誰とでも瞬時につながることができます。ビデオ通話で離れた家族と話し、SNSで世界中の人と交流し、リアルタイムで情報を共有できます。インターネットに代表される通信技術やスマートフォンなどのデバイスの進化によって、ここ数10年で人々の「つながる力」は飛躍的に高められました。
しかし皮肉なことに、こうした技術の発展は、必ずしも人々の心理的・感情的な隔たりを近づけたとは限りません。むしろ近年では、社会の分断や個人の孤立といった現象がますます深刻化しています。SNSに代表される「同質性の高いつながり」は、異なる価値観との接点を減らし、社会的な理解や共感を阻む温床にもなり得ます。過剰な情報がかえって人々の注意力を奪い、本質的なコミュニケーションの質を低下させているという指摘も少なくありません。
さらに、情報の信頼性や共有のあり方も課題となっています。誰もが発信者になれる一方で、フェイクニュースや陰謀論といった誤情報が拡散されやすくなり、社会の分断をあおる要因となることもあります。テクノロジが進化したにもかかわらず、人々の間には「情報の壁」や「感情の距離」が存在し、それが誤解や対立を生み出しています。
このような背景のもと、NTTは「つながる」ことの意味をあらためて見直し、分断を乗り越えるための未来のコミュニケーションのあり方を探求しています。そして、その挑戦の一環として取り組んでいるのが、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)での出展です。
万博に取り組む意義 ~未来のコミュニケーションの提案~
NTTは、通信という社会基盤を支える存在として、その前身である日本電信電話公社時代から現在に至るまで、万博やスポーツ大会といった世界的なイベントを通じて未来のコミュニケーションのあり方を積極的に提案・実践してきました。
1970年の日本万国博覧会では、世界で初めてワイヤレス通信システムを実用化(図1)することに成功しました。来場者が自由に手にとって、全国どこへでも通話ができる「パーソナルコミュニケーション」の実験を実施しました。これにより「固定された場所で受ける」通信から「個人が自由な場所で使える」通信への発想の転換が生まれ、後の携帯電話やスマートフォンにつながる礎となりました。

1998年の世界的なスポーツ大会では、PHSマルチメディア通信や腕時計型PHS(図2)の実験を通じて、「ウェアラブルコミュニケーション」の未来像を提示しました。当時としては革新的だった人が身につけるデバイスは、今やスマートウォッチやイヤホン型端末など、当たり前の技術となっています。

コロナ禍という特殊な状況の中で、2021年に開催された世界的なスポーツ大会でも、最新の通信技術により次世代の「パブリックビューイング」の実験を実施しました。超高臨場感通信技術Kirari!をセーリング競技やバドミントン競技に適用し、実際の競技会場の「臨場感」を別の場所に再現(図3)することができました。また超低遅延通信技術をマラソン競技に適用することで、距離を超えた「一体感」を醸成することにもチャレンジするなど、選手と観客をつなぐ「スポーツ観戦」の未来像を提案しました。

NTTはこれまで、人々がいかにすればより深くつながれるのかを追求してきました。2025年の大阪・関西万博においても、未来のコミュニケーションの創出に取り組みました。本プロジェクトは、現代社会における分断や孤立といった課題に対し、次世代テクノロジを活用して新たなつながりのあり方を模索する試みです。高度な通信技術が普及する一方で、共感や気配といった非言語的な要素はいまだ十分に伝えることができません。IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)時代のコミュニケーションは、こうした繊細な感覚にも対応し、人と人との本質的な理解を支える手段へと進化していきます。NTTパビリオンでは、つながりの質を高めるとともに、多様で柔軟なつながりのかたちを生み出し、未来の社会における新たなコミュニケーションの可能性を提示しています(図4)。

未来のコミュニケーションのあり方 〜共感と関係性を支える2つの進化〜
未来のコミュニケーションは、大きく2つの方向に進んでいくと考えられます。1つは、コミュニケーションの質の向上によって、より深い共感や心理的な安心感を育む方向。もう1つは、これまでになかった多様な関係性──例えば「未来の自分」や「空間・環境」との対話──を通じて、社会や自己とのつながり方そのものを拡張する方向です。
■コミュニケーションの質の向上による共感の醸成
現代社会では、リモートでのやり取りが日常化する一方で、「相手が本当にそこにいる」と感じにくい、あるいは「自分の存在が伝わっていない」と感じる瞬間が増えています。こうした「実在感」の欠如が、孤立や誤解を助長しているのが実情です。
この課題に対して、空間全体の共有感覚を高めるコミュニケーション環境が1つの解決策になると考えています。例えば、離れた空間どうしをリアルタイムで統合し、まるで1つの空間にいるような体験を実現することは、協働や共感の基盤をつくり出します。学校、職場、地域、文化圏を越えた人々が同時に「そこにいる」という感覚は、分断された社会の再接続に貢献します。今回の大阪・関西万博では、吹田市の万博記念公園の特設ステージ上のパフォーマンスを、周囲の空間情報と一緒にまるごとリアルタイムで伝送。夢洲のNTTパビリオンに再現することで、まるで相手が隣にいるような、存在を感じるコミュニケーション体験を提供しました。詳細は本特集記事『IOWN×空間伝送――離れた空間が1つになるコミュニケーション体験』で紹介します。
また、1対1のリモートコミュニケーションにおいて、視聴覚に加えて触覚を共有することも、人と人との感情的距離を縮める手段として重要です。遠くにいる家族と手のぬくもりを感じ合う、言葉にできない感情を「触れ合う」ことで伝える――このような感覚的なコミュニケーションは、安心感や共感を深めるだけでなく、介護や医療、教育などの領域でも新たな支援のかたちを提供します。今回の大阪・関西万博では、映像と音声に加えて触覚・振動を送り合うことができる端末を会場内外の複数個所に設置。初めて会う人とでも気軽に触れ合うコミュニケーションができる「未来の電話」をつくることにチャレンジしました。詳細は本特集記事『コミュニケーションのあり方を問いかける「ふれあう伝話」と「せかいがきこえる伝話」――電話から、伝話へ』で紹介します。
これらの進化は、単にリモートコミュニケーションを「リアルに近づける」ことが目的なのではなく、「心が通い合っている」と実感できるような“深いつながり”を育み、共感や安心感を醸成する基盤になると考えています。
■多様なコミュニケーションによる新たな関係性の構築
もう1つの方向性は、これまで接点がなかったものとの関係性の再構築です。AI(人工知能)の進展により、言語や文化の違いを超えた人と人のつながりはもちろん、従来の枠を超えて、自分自身や自身を取り巻く環境とのつながりが、新たな関係性を生み出す鍵となります。
デジタルヒューマンなど、AIを通じた自分自身とのコミュニケーションはその代表例です。過去・現在・未来の自分と対話することで、自己の価値観や目標、変化に気付き、深い内省と自己肯定感が促進されます。このような自分自身とのコミュニケーションは、個人の精神的な安定や自己成長に寄与するだけでなく、他者との関係においてもより成熟したつながりを生む土台になると考えられます。今回の大阪・関西万博では、デジタルのもう一人の自分である「Another Me®」との対話を通じて、自身の新たな可能性に気付くことができるコミュニケーション体験の提供にチャレンジしました。詳細は本特集記事『Another Me Planet――未来の可能性を見せる自分の分身』で紹介します。
さらに、感情に応答する建築や都市とのコミュニケーションも新たな潮流です。人の心に呼応して光や音、空間構成が変化するインタラクティブな環境により、人の内面が可視化・共有されることで、他者との感情的なつながりが生まれやすくなります。今回の大阪・関西万博では、NTTパビリオン来場者の表情や盛り上がりを分析し、その結果をNTTパビリオンのファサード(幕)に反映させて人工的に幕を揺らしています。揺れている幕や音に気付いたパビリオンの外の人が、NTTパビリオンに興味を持っていただけると、中と外が通じ合います。そんなモノを介した多様な人とつながりあえる未来の先駆けとなる技術を実装しました。詳細は本特集記事『感情を纏うパビリオン――ヒトとモノが呼応するコミュニケーション体験』で紹介します。
なお、こうした「自分」や「モノ」との新たな関係性の探求に加えて、NTTパビリオンでは言語の壁を越える新たな技術も導入しています。有名アスリートの一言語の音声からクロスリンガル音声合成技術を用いて多言語音声を生成し、6カ国語による紹介アナウンスを実現しました。この技術により、声質を維持しつつ言語の壁を越えた情報伝達が可能となり、多様な聴衆との関係構築に役立ちます。声だけで、世界中の人々とつながるコミュニケーションの可能性が広がっているのです。
おわりに
未来のコミュニケーションに関する取り組みは、単に先端技術を誇示するものではありません。私たちが大阪・関西万博で提案するのは、人と人、人と空間、さらには人とモノといった新しい関係性を再構築するための問いかけでもあります。これからの社会では、テクノロジを前提とするだけでなく、人の感性や倫理、文化と調和するかたちで設計されたコミュニケーションが求められます。例えば、AIが人の感情を理解し、会話をより自然なものにする。センサが空間の反応をきめ細かくフィードバックし、安心感のある対話を実現する。こうした技術は、冷たく機械的なものではなく、むしろ人間らしさを引き出す装置として機能する可能性があります。
私たちは、こうした人間中心の未来像を見据え、社会とともに成長するテクノロジのあり方を模索しています。分断を越えて多様な人々が理解し合い、協働し合う社会。それを可能にする新たなインフラとして、未来のコミュニケーションのかたちを提案していくことが私たちの使命です。2025年の大阪・関西万博は、その第一歩となる場です。これからの10年、20年を見据え、私たちは真に“つながる”社会の実現に向けて、技術と人間性の橋渡しを続けていきます。

(上段左から)日高 浩太/島村 潤
(下段左から)望月 崇由/平尾 美佐
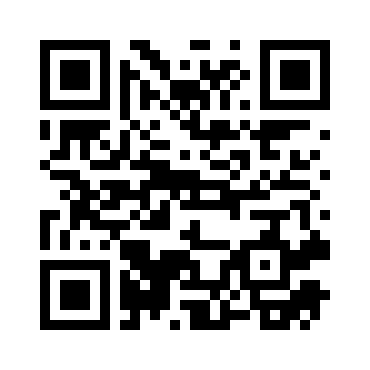






未来のコミュニケーションは、テクノロジを前提とするだけでなく、人間の感性や文化と調和ししながら、新たな関係性を築くものであると私たちは考えています。大阪・関西万博をその出発点として、今後も人間中心の社会を支える技術のあり方を模索・提案していきます。