-
- DECEMBER 2025号
-

- 沈黙のリスク、崩れゆく基盤(後編)―最新技術動向と次世代の展望
- 前編では、インフラ老朽化問題について、我が国の制度の推移、予算・政策の方向性、そして過去に起きた代表的な事故事例を通じて、現場が抱える構造劣化リスクの深刻さをについて述べてきました。道路の陥没、橋梁の落橋、トンネル壁の剥落等の事故は、さまざまな複合因子を介して引き起こされており、全国各地でいつ発生しても不思議ではないほど、劣化の予兆が表面化している状況を確認しました。後編では、インフラ老朽化に対応するための最新技術動向を中心に据え、検査・検知・復旧・予防の観点から、現在、研究・適用されている主な技術を紹介します。そして最後に、全編を踏まえ次世代につながる社会インフラのあり方について考えます。
- 詳しく見る
-
- NOVEMBER 2025号
-

- 沈黙のリスク、崩れゆく基盤(前編)-インフラ老朽化の現状と政策の岐路
- 日本では高度経済成長期(1950~60年代)に集中的に整備された社会インフラが、築後50年以上を経過し、急速に老朽化しており、戦略的な維持管理・更新が喫緊の課題となっています。前編では、インフラ老朽化の現状と課題について整理し、後編において、点検・検知や修理・復旧のための最新技術動向と今後のあるべき姿について海外事例も含め解説します。
- 詳しく見る
-
- SEPTEMBER 2025号
-
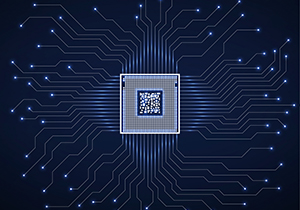
- 新たなデジタル社会を切り拓く「光電融合」:世界で開発が加速-後編-
- 本誌連載の前編では、光電融合技術が注目されている背景、光電融合技術とは何かとその主要技術を紹介してきました。後編では、光電融合分野における主要プレイヤの技術動向と特許出願状況、半導体メーカやスタートアップ、通信機器ベンダなどの具体的な取り組みを詳しく紹介します。また、技術普及における課題と今後の展望についても解説し、光電融合技術が社会に与える影響を考察します。
- 詳しく見る
-
- AUGUST 2025号
-
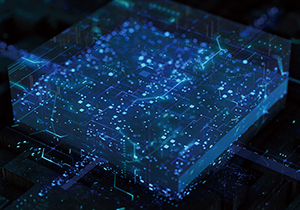
- 新たなデジタル社会を切り拓く「光電融合」:世界で開発が加速-前編-
- デジタル社会の急速な進展に伴い、データ処理量は急激に増加している中で、従来の電気信号だけに依存した情報処理技術は物理的限界に直面しています。光と電気の特性を融合させることで通信・コンピューティングの高速化と低消費電力化を同時に実現する「光電融合技術」が注目されています。国内外で注目されている背景、その主要技術と期待されている利用シーンについて解説します。
- 詳しく見る
-
- JUN 2025号
-

- 量子コンピュータで社会やビジネスはどう変わるか-後編-
- 量子コンピュータ技術は発展途上にありますが、量子コンピュータが新たなビジネスになることを見越して、現時点の技術を活用して、量子コンピュータを商用化する動きがみられます。また、海外の大手IT企業、ベンチャー企業、また日本企業なども商用化に向け積極的な動きをみせています。本稿では、上記のプレイヤの動向を紹介するとともに、現状でのビジネスモデルについて整理します。また、量子コンピュータの具体的な利用シーンに触れ、実用化に向けた動きがあることを紹介します。
- 詳しく見る
-
- MAY 2025号
-

- 量子コンピュータで社会やビジネスはどう変わるか-前編-
- 量子コンピュータ関連技術がここ数年で大きく進化し、実用化に向けた議論が行われています。その一方で、量子コンピュータをはじめとする量子技術の本格的な導入はまだ先だという議論もあるのが現実です。本稿においては、量子コンピュータをはじめとする量子技術、量子コンピュータの特徴と可能性、またその技術的、ビジネス的課題について概説します。また、量子コンピュータ等が社会に大きなインパクトを与える可能性が明らかになるにつれ、国家レベルでの開発戦略が進んでいることについて米国、欧州、中国、日本を例にその内容について紹介します。
- 詳しく見る
-
- MARCH 2025号
-

- 観光地経営の現在地と観光DX-後編-
- 前編では、日本人にとっての「観光地」の変遷について「観光資源」に着目しながら歴史的に振り返りました。コロナ禍がもたらしたインパクトを確認するとともに、観光地経営に求められる「情報の重要性」について俯瞰しました。後編では、2024年現在の「観光地経営の現在地」について、観光を取り巻く環境を、PEST分析の観点(政治、経済、社会、技術)で俯瞰しながら、観光DX(デジタルトランスフォーメーション)の事例について紹介します。これらを通じて、DXが観光地経営に貢献し得る意義を再確認するとともに、新たに付加価値を生む可能性や新たなビジネスチャンスの萌芽を見出すことを目的とします。
- 詳しく見る
-
- FEBRUARY 2025号
-

- 観光地経営の現在地と観光DX-前編-
- 2023年5月の新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行以降、日本国内の観光産業は全般的に上向きの兆しがみられ、コロナ禍前のペースを取り戻しているようにもみえます。昨今の円安基調も相まって、海外から日本を訪れるインバウンド観光客は、大幅な増加傾向にあります。引き続き、政府主導の地方創生を目的とした新たな経済対策なども期待されています。直近、2024年9月の訪日外客数は、287万2200人で、前年同月比では31.5%増、2019年同月比では26.4%増となり、8カ月連続で同月過去最高を記録しています。また円安の影響もあって訪日客の消費額も増えていて、日本経済新聞(2024年8月21日)によると、訪日客の2024年1〜6月の消費額は3兆9070億円、財務省の貿易統計で同期の主要な輸出品目と比べると、半導体等電子部品(2兆8395億円)を上回るほどです。本稿では、日本の観光に着目して、その歴史的な観点からの「現在地」を再確認するとともに、コロナ禍以降観光地が抱える課題やポイント、さらには観光DX(デジタルトランスフォーメーション)が求められる背景や事例について紹介します。前編では、日本人にとっての「観光地」の変遷について「観光資源」に着目しながら歴史的に振り返ります。コロナ禍がもたらしたインパクトを確認するとともに、観光地経営に求められる「情報の重要性」について俯瞰します。
- 詳しく見る
-
- DECEMBER 2024号
-

- ビジネスのイネーブラーとしてのセキュリティ-後編-
- セキュリティが事業の「イネーブラー」、すなわちビジネスの価値提供に不可欠なものとなっている海外事例を紹介します。1つは、SBOM(Software Bill Of Materials)により実現している高度なモビリティサービスの事例、もう1つは、セキュリティソリューションの組合せによって医療情報が利用可能となっている事例です。これらの内容と、セキュリティが実現した価値について紹介し、セキュリティが新たなビジネスと不可分なものとなっていることについて述べます。
- 詳しく見る
For the Future
NTT技術ジャーナル編集部が注目する業界の最新動向をご紹介します。

