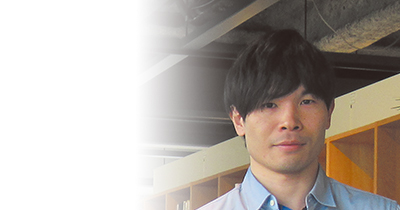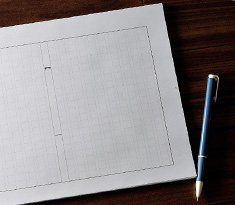-
- 2026.02.16
グローバルスタンダード最前線 -

- ITU-T SG15(Networks, technologies and infrastructures for transport, access and home)第2回本会合の動向
- 2025年10月13~24日に2025-2028年会期のITU-T(International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector) SG15(Study Group15)第2回本会合がスイスのジュネーブで開催されました。本稿では特に、光アクセスネットワーク、ならびに光物理層標準に関する第2回SG15本会合の動向について報告します。
- 2026.02.16
-
- 2026.01.21
グローバルスタンダード最前線 -

- ITU-T SG12 標準化動向
- 通信サービスを適切な品質で提供するために、ネットワークおよびサービスの設計・管理は極めて重要で、そのためには、定量的に品質を測定・評価する技術が必要となります。ITU-T(International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector) SG(Study Group)12では、ユーザがサービスに対し、体感する品質(QoE:Quality of Experience)とその目標値を達成するために要求されるネットワーク品質(QoS:Quality of Service)の評価法、測定法、規定値等に関する研究を行っています。ここでは、映像メディアの品質評価・管理技術に関する最新の標準化動向を中心に紹介します。
- 2026.01.21
-
- 2025.12.16
グローバルスタンダード最前線 -

- 2027年ITU世界無線通信会議(WRC-27)に向けた最新動向
- 世界無線通信会議(WRC:World Radiocommunication Conference)は、国際電気通信連合(ITU:International Telecommunication Union)が主催する国際会議で、無線通信に関する国際的なルールである無線通信規則(RR:Radio Regulations)の改正を主たる目的としています。次回は2027年の開催予定ですが、すでに、ITU-R(ITU-Radiocommunication Sector)研究グループ、地域グループ、国、それぞれにおいて事前検討、合意形成に向けた議論が本格化しつつあります。RRの改正内容は国内の電波法令等にも反映されることから、携帯電話等の無線によるサービスを提供しているNTTグループにとって非常に重要な会議です。本稿では、WRC-27の主な議題、および検討状況について概説します。
- 2025.12.16
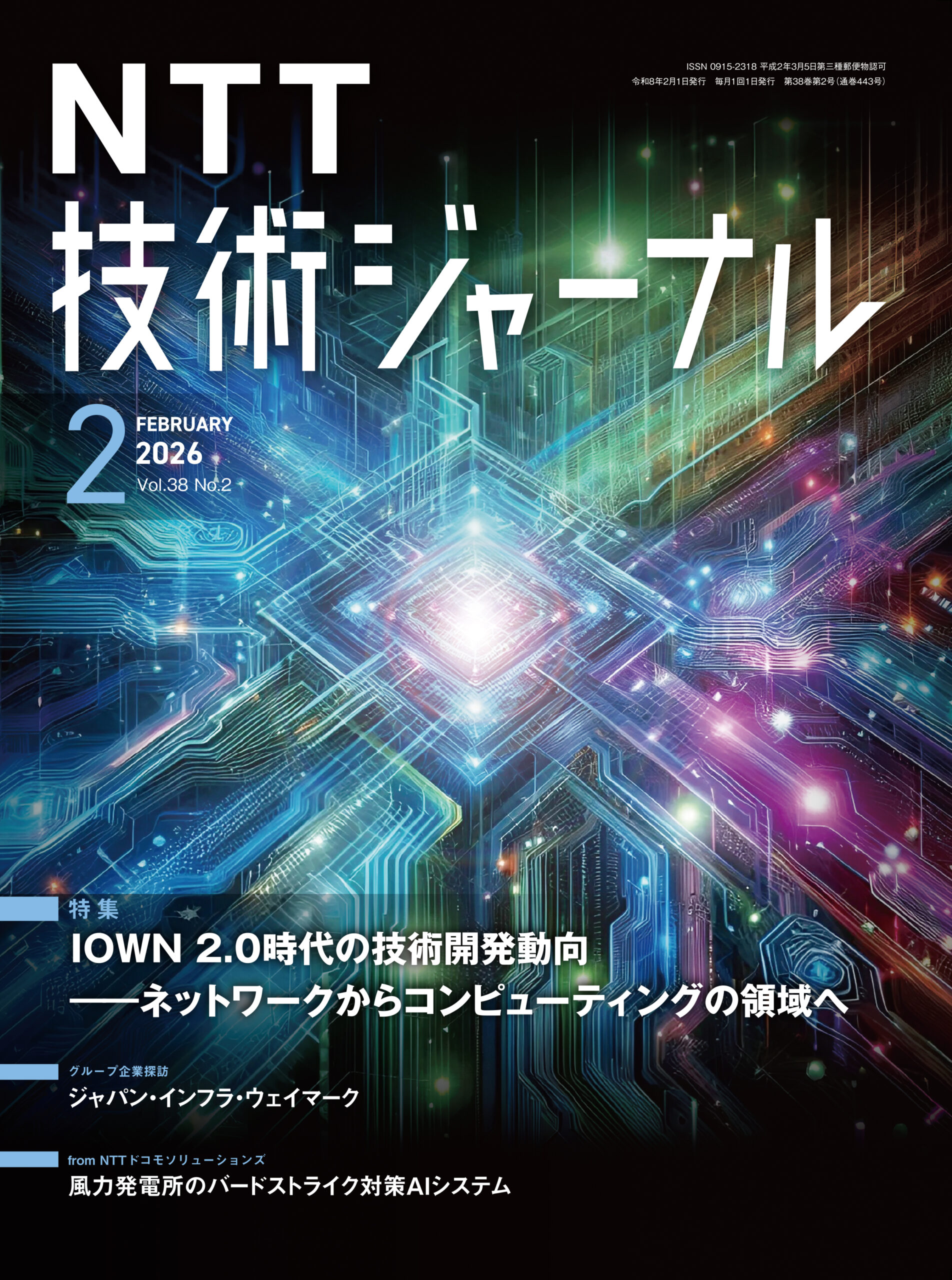
- 2FEBRUARY 2026vol.38
- 最新号
- NTT技術ジャーナル 2026年2月号
発行日 2026年2月1日
(Web) ISSN 2758-7266 / (冊子) ISSN 0915-2318 - 冊子PDFダウンロード
-
- 特集
-

- IOWN 2.0時代の技術開発動向――ネットワークからコンピューティングの領域へ
- IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想は、2023年のAPN(All-Photonics Network)サービス開始に続き、コンピューティング領域へ進展していく。NTT IOWN総合イノベーションセンタ(IIC)は、IOWN 光コンピューティングを社会実装していくために、DCI(Data-Centric-Infrastructure)のマルチベンダ化やAPNの普及拡大をめざした技術開発などを行っている。本特集ではIICに属する各センタの取り組みを紹介する。
-
- 挑戦する研究者たち
-

- 学ぶ場、働く場、そして研究の場のウェルビーイング・コンピテンシー
- 昨今、経済的な価値だけでは測れない人の存在や心のあり方に価値をおいたウェルビーイング(Well-being)の重要性が高まっています。また、技術の急速な発展や社会情勢の劇的な変化など、先を予測できない時代では、多様な価値や急転する状況に合わせていく柔軟な思考力や行動力を持ち、皆で道筋をつくり調整しながら目標に向かい進んでいくことが必要です。NTTコミュニケーション科学基礎研究所の渡邊淳司上席特別研究員は学校教育や企業活動における実践の場でウェルビーイング・コンピテンシーを身に付け、実際に活用できる具体的な手法を提案、展開しています。今回は、最近、特に注力している領域や自身の研究スタイルについて伺いました。
-
- 挑戦する研究開発者たち
-
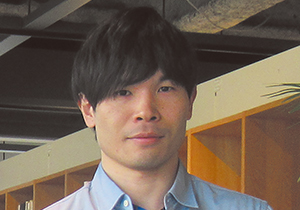
- 情報処理技術の専門家として建物環境のIT化を牽引する
- 人がオフィス内で暑さ、寒さを感じる要因とは何でしょう。それはエアコンで制御される温度や湿度、風速だけではありません。人が身に付けている衣服の着衣量や人自身の活動量も重要な因子になります。NTTファシリティーズの中満達也氏は、AI(人工知能)に基づいた空調制御技術で建物の省エネルギー化に取り組むとともに、オフィス在室者が感じる快適性の定量化についても情報処理技術の切り口から挑んでいる、建物IT分野のスペシャリストです。今回、最新の検証状況に加え、建物の設計・維持管理を本業とする企業でのIT技術者としての思いや今後の研究ビジョンについて伺いました。
-
- 明日のトップランナー
-

- 光通信の限界を突破する、InP系半導体の極広帯域アナログIC
- 増大する通信トラフィックを支える通信環境の進展は、デジタル信号処理や集積回路の性能改善によって支えられてきました。しかし昨今、ハードウェア性能の制約で抜本的な改善が見通せない状況が顕在化しつつあります。この問題に風穴を開けるのが、「極広帯域アナログIC」技術です。この新技術によって、従来のシリコン系半導体の微細化による性能改善だけに頼った方法からの脱却が可能となります。今回はこの「極広帯域アナログIC」のトップランナー、長谷宗彦特別研究員にお話を伺いました。
-
- グループ企業探訪
-

- メンテナンス技術×ICT・AI技術×ドローン技術で“支える人を、支えたい”
- 高度経済成長期に整備された日本のインフラ設備は、敷設から50年以上が経過し、老朽化が深刻な課題となっています。加えて、維持管理にかかわる技術者不足と財源不足は年々深刻化しており、従来の点検手法だけでは対応が困難な状況にあります。このような「100年に一度の大転換期」にある社会課題の解決に向け、ドローンとICTを駆使したインフラ点検サービスで注目を集めているのが、ジャパン・インフラ・ウェイマークです。2019年の設立以来、全国6200件以上もの橋梁、鉄塔、道路で点検を手掛けてきました。今回、矢倉良太社長に事業内容、最新の取り組み、および「支える人を、支えたい」というミッションに込めた思いについて伺いました。
-
- from NTTドコモソリューションズ
- 風力発電所のバードストライク対策AIシステム
- 再生可能エネルギーの1つである風力発電事業では、飛来する鳥の風車ブレードへの衝突(バードストライク)が野生生物保全と風力発電推進の両立をめざすうえで課題となっています。周辺の自然環境との調和とともに社会インフラを維持することが重要視される中で、その対策が求められています。NTTドコモソリューションズはAI(人工知能)活用による「バードストライク対策AIシステム」(広角カメラで遠方の鳥を検出、PTZカメラで追尾拡大撮影、AIで鳥種を画像判定するシステム)を開発し、風力発電事業者と共に各地のフィールドで実証を行っています。本稿ではこのシステムの必要性と技術について解説します。
- 詳しく見る